
競争が激化する現代ビジネスでは、持続的な成長を実現するためには明確な事業戦略が不可欠です。しかし、戦略策定に課題を感じている経営者の方も少なくないでしょう。そこで注目されるのが「事業戦略コンサルティング」です。 本記事で […]
競争が激化する現代ビジネスでは、持続的な成長を実現するためには明確な事業戦略が不可欠です。しかし、戦略策定に課題を感じている経営者の方も少なくないでしょう。そこで注目されるのが「事業戦略コンサルティング」です。
本記事では、事業戦略コンサルティングがどのように競争優位の確立に貢献するのかを解説します。さらに、混同されやすい「ビジネスコンサルティング」との違いを明確にし、貴社にとって最適なコンサルティングの選択肢を提供します。
事業戦略コンサルティングとは?
企業が持続的な成長を遂げ競争優位を確立するためには、将来を見据えた周到な事業戦略が不可欠です。ここでは、事業戦略コンサルティングの主要な支援領域や主な支援対象者とプロジェクトの特性、そしてコンサルタントに求められるスキルを解説します。
戦略コンサルの主な支援領域
事業戦略コンサルティングでは、多岐にわたる経営課題に対して包括的な視点から支援を行います。中心となるのは、中長期ビジョンの明確化や市場および競合環境の分析に基づく成長戦略の設計です。加えて新規事業の構想立案や海外進出、M&Aを含む企業変革の構想まで幅広く対応しています。
特定の施策にとどまらず企業の未来像を描き、それに至るまでの実行可能な道筋を示す役割を担います。例えば、国内市場が成熟する中で新たな収益源の必要性が高まっている企業に対しては、グローバル展開や他社との統合による事業拡大を見据えた提案が行われるでしょう。
このように、戦略コンサルタントは企業全体の構造変革や成長の推進を支える存在として活用されます。
支援対象者とプロジェクトの特性
事業戦略コンサルティングの支援対象者は主に経営者や経営陣であり、組織全体の戦略的課題を解決するための支援を行うのが大きな特徴です。日常的な業務改善ではなく、企業の将来に影響を与える構想の立案や意思決定を支える役割が求められます。
特に過去のデータや前例では対処が難しい非定型の課題や、数年先を見据えた未来志向のテーマに焦点を当てるケースが多く見られます。例えば、脱炭素社会への対応やデジタル変革などのテーマでは、企業独自の立ち位置や強みを活かした戦略を構築する必要があるでしょう。
以上のようなプロジェクトでは、柔軟な発想力と同時に経営層との対話を通じて意思決定を促す関係構築も欠かせません。このような背景から戦略コンサルは、経営の最前線で未来を創る支援を担うポジションとして注目されています。
事業戦略コンサルタントで求められるスキル
事業戦略コンサルタントには、高度な専門性と幅広いスキルが求められます。特に、複雑な情報を整理し筋道を立てて物事を捉える論理的思考力と、それを裏づける定量的・定性的分析力はマストなスキルです。
加えて、明確に定義されていないテーマに対して適切な課題を抽出し、方向性を導き出す力も重視されます。さらに、経営層や多様なステークホルダー(利害関係者)との対話を円滑に進め、議論を深めながら信頼関係を築くファシリテーション能力も不可欠です。
例えば新規事業の立ち上げでは、最初は漠然としたアイデアを具体的な施策へと落とし込んでいく必要があります。このプロセスの中でこそ、事業戦略コンサルティングのスキルが真価を発揮します。
事業戦略コンサルタントは思考力と対話力を併せ持つ専門家として、経営課題の本質に迫る役割を果たす存在です。
関連記事:事業戦略と営業戦略の違いとは?役割と成功ポイントを解説
事業戦略コンサルティングで競争優位を確立するステップ

ここでは、事業戦略コンサルティングの主要なプロセスを4つの段階に分けて解説します。
現状の分析
競争優位を確立するための最初のステップは、自社の現状を正確に把握・分析することです。自社の現状を正確に把握するには、SWOT分析を用いると効果的です。企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を明確にし、内部環境と外部環境の両側面から自社の立ち位置を客観的に評価できます。
また、現状分析では経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいた意思決定が必要です。市場調査データ、顧客データ、競合データ、財務データなど様々なデータを収集・分析し、現状を数値化することでより精度の高い戦略立案が可能になります。
SWOT分析の活用とデータ主導の意思決定を組み合わせることで、競争優位を築くための強固な基盤を構築します。
戦略の立案と実行計画
現状分析が終わったら、戦略立案と実行計画に移りましょう。
戦略の立案では、まず自社の現状分析(SWOT分析やPEST分析など)を通じて、外部環境と内部資源の把握を行うことが出発点となります。そして、戦略を立案したうえで長期的なビジョンを策定し、どの市場で・どのような価値を・どのように提供するのか基本方針を明確にしましょう。
次に、戦略のビジョンを現実に落とし込むための中期・短期の目標を設定し、KPI(重要業績評価指標)やマイルストーンを含んだ実行計画を策定します。ここでは、リソース配分、スケジュール、責任分担などを明記したアクションプランが不可欠です。
また、戦略実行のフェーズではPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを導入し、進捗の可視化と柔軟な調整が求められます。市場環境が急速に変化する現代では、計画は固定的なものではなく、常に見直し可能な「動的な戦略」としての設計が大切です。
柔軟な発想に基づく戦略立案と、具体的かつ段階的な実行計画の設計を組み合わせることで、競争優位の確立と持続的成長が可能となるでしょう。
成果の測定と改善
戦略の実行が開始された後は、その進行状況を継続的に把握して必要に応じた軌道修正が求められます。KPIの設定は、目標とのギャップを明確に可視化し、課題の早期発見を可能にします。
単なる数値の追跡にとどまらず、なぜその数値が変動したのかを分析して施策の有用性の検証が必要です。さらに、成果をもとに学びを得て次の施策へと反映させる仕組み、すなわちフィードバックループを社内に定着させることが中長期的な成長につながります。
例えば営業戦略を見直した企業が、商談成立率をKPIとして分析を行い、その結果に基づいて人材育成プログラムを再設計したことで、売上高の大幅な向上を実現しました。戦略の実効性は、継続的な測定と改善によって支えられています。
事業戦略コンサルを活用した成功例から学ぶ
事業戦略コンサルティングを通じて大きな変革を遂げた企業の事例からは、現実的な学びを得ることが可能です。単なる成功体験の紹介ではなくどのような課題に直面し、それをどう乗り越えたのかなどのプロセスにこそ注目が集まります。
例えば、長年一般消費者向け(BtoC)に家庭用製品を提供していた老舗の製造業が、市場の成熟と縮小という構造的な課題に直面したとします。この企業では、事業戦略コンサルタントの支援を受け事業ポートフォリオの再構築を図り、BtoC事業からBtoB事業への転換に踏み切りました。
コンサルタントと協働で市場分析や競合調査を実施し、自社技術の強みを生かせる法人向け製品への展開を決定します。新たな収益モデルの設計、営業チャネルの再構築、組織体制の見直しを行い、さらにはグローバル市場への展開も視野に入れた戦略を策定しました。結果的に、業績はV字回復し持続的な成長軌道に乗ることができました。
具体的なストーリーからは、戦略的思考の有用性と変革を推進するための実行力の両面を学ぶことが可能です。事業戦略コンサルティングの真価は、成果を創出する支援にこそあります。
ビジネスコンサルティングとは?

企業が直面する様々な経営課題に対し、専門的な知識や経験に基づいて解決策を提供するのがビジネスコンサルティングです。ここでは、ビジネスコンサルティングの主要な支援領域、プロジェクトの進め方と特徴、そしてコンサルタントに求められる要素を解説します。
ビジネスコンサルの主な支援領域
ビジネスコンサルティングの対象領域は幅広く、企業活動の多くの側面に対応します。中でも、業務プロセス全体を見直し抜本的な再設計を行うBPR(Business Process Re-engineering)は中心的な支援内容の一つです。
また、売上向上を目的とした営業体制の見直しや、マーケティング施策の実行支援を通じた顧客獲得力の強化も重視されます。さらに、部門をまたいだ非効率の排除やコスト構造の最適化など、企業全体に波及する改革も対象です。
例えば、ある製造業で生産から販売までの業務を横断的に見直し、不要な工程や重複作業を排除した結果、大幅な納期短縮とコスト低減を実現しました。ビジネスコンサルは、具体的かつ実行可能な改革を通じて企業活動の質を高めます。
プロジェクトの進め方と特徴
ビジネスコンサルティングでのプロジェクトは、実行を前提とした短期から中期にかけての支援が多くを占めています。抽象的な提案に終始せずに実際の業務に根ざした改善を行うため、現場担当者と密に連携を取りながら課題の抽出と対応策の策定を進める点が特徴です。
さらに、成果を可視化するためにKPIを明確に設定し、定量的な指標を通じて進捗状況と成果の測定が行われます。
例えば、あるサービス業の現場改善プロジェクトでは、顧客対応のリードタイム短縮をKPIとし業務の流れを見直したことで、クレーム件数の減少と顧客満足度の向上を同時に達成しました。ビジネスコンサルでは現場に入り込む姿勢と数値に基づく評価軸を重視し、現実的かつ継続可能な変化を生み出します。
ビジネスコンサルタントに求められる要素
ビジネスコンサルタントには、対象となる業務に対する深い理解と現場で得られた知見の活用が求められます。単なる理論や知識だけでは実行支援の説得力が欠けるため、現場での対応経験や業界特有の慣習に対する理解が成果を左右します。また、現場の状況は日々変化するため、柔軟に対応しながら最適な解決策を導き出す応用力も不可欠です。
例えば、複数店舗を展開する小売業を支援したプロジェクトでは、地域ごとの事情に応じて販売戦略を微調整しながら全体最適を実現しました。その過程で、担当コンサルタントの柔軟な対応力と調整力が成果のポイントとなったのです。実務に根差した知識と対応力を兼ね備える人材こそが、ビジネスコンサルティングで高い成果を導き出せます。
事業戦略コンサルティングとビジネスコンサルティングの違いとは?
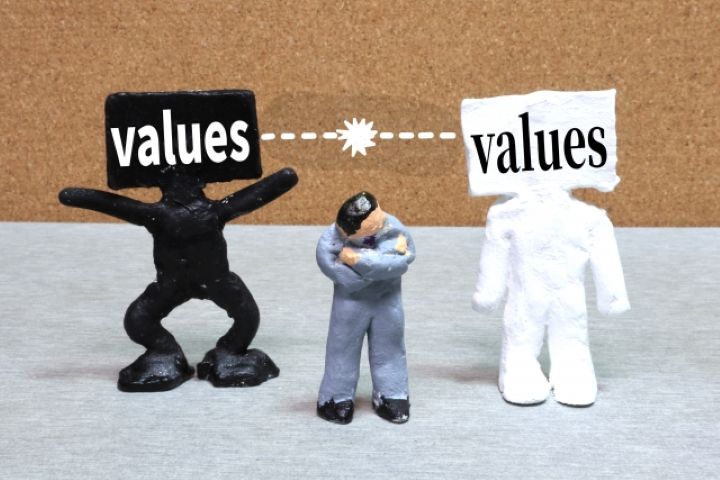
企業の経営課題を解決するコンサルティングには、事業戦略コンサルティングとビジネスコンサルティング、2つの主要な形態が存在します。ここでは、これら2つのコンサルティングの違いを解説し、それぞれの特性を踏まえた上でどのような企業のフェーズやニーズに適しているのかを見ていきましょう。
支援の目的とアプローチの違い
事業戦略コンサルティングでは、企業の中長期的な成長を見据えたビジョンの提示や、大局的な方向性の策定が主な目的となります。一方、ビジネスコンサルティングでは現在直面している課題に対して、実務レベルでの具体的な解決を重視するのが特徴です。
事業戦略コンサルティングは抽象度の高い仮説構築や外部環境分析を基にした将来像の設計に長けており、ビジネスコンサルティングは目の前の業務効率化や売上改善など現場起点の改革に焦点を当てます。
例えば、事業戦略コンサルでは「5年後に市場でどのような立ち位置を目指すか」などのテーマに取り組み、ビジネスコンサルでは「今期の営業プロセスをどう改善するか」などの視点で提案が進められます。両者のアプローチは異なりますが、経営と現場をつなぐ連携が図れればより実効性のある変革を進めやすくなるでしょう。
関与する層とコミュニケーションの違い
コンサルティングの進め方では、関与するステークホルダーの層によってコミュニケーションの内容も大きく異なります。事業戦略コンサルティングでは、企業の将来像や資源の再配分など経営判断を支援するため、主に経営陣と直接対話を重ねながら進行します。
議論の内容は抽象度が高く意思決定への影響も大きいため、長期視点での合意形成が欠かせません。一方、ビジネスコンサルティングでは業務改善や実行支援が中心となるため、部門長や現場スタッフとの連携機会が多くなります。
具体的には、業務プロセスの見直しであれば日々の業務に携わる担当者にヒアリングを行い、細かな運用課題を抽出しながら改善施策を立案していきます。それぞれの対象層に合わせた対話力と理解力が、プロジェクトの成果に直結していくでしょう。
提供する成果物の違い
プロジェクトのアウトプットにも、両者の役割の違いが明確に現れます。事業戦略コンサルティングでは、将来の事業成長や変革を見据えた中長期な提言書や複数のシナリオを想定したシナリオプランニング資料、企業の成長を図示する成長マップなど、上位概念に基づいた成果物が中心です。
抽象的な内容であっても経営層の意思決定を支援するために設計され、経営の方向性に大きな影響を与える役割を果たします。一方、ビジネスコンサルティングでは現場での実装を見据えた業務フロー図やKPIレポート、改善提案書など実務に即した成果物が多いです。
具体的には、業務の属人化を解消するための標準化マニュアルの作成などがあります。どちらの成果物も対象とする課題に応じて細かい点までに設計されており、目的達成に向けた実用性が求められるでしょう。
導入企業のフェーズやニーズによる適正の違い
企業が抱える課題や置かれているフェーズによって、どのタイプのコンサルティングが適しているかは異なります。事業戦略コンサルティングは、企業が新たな市場に挑戦する場面や全社レベルでの再編を必要とする経営改革期など、抜本的な意思決定を要する局面で強い支援効果を発揮します。
将来を見据えたビジョンの再構築や競争優位の源泉となるポジション確立などに対して、論理的かつ俯瞰的な視点からアプローチが進められます。対してビジネスコンサルティングは既存事業の効率向上や業務プロセスの見直しなど、日常的な経営課題に対して即効性のある支援が可能です。
具体的には、業務の属人化や非効率な課題の是正に取り組む現場改善プロジェクトなどが挙げられます。目的やフェーズに応じて適切なコンサルを選定する判断が、成果を左右する要素です。
関連記事:事業開発とマーケティングの違いを明確化!定義と目的、スキルの全貌
事業戦略コンサルとビジネスコンサルの連携による相乗効果

事業戦略コンサルティングとビジネスコンサルティングの連携によって、企業の変革プロジェクトでの実効性と持続性を高めやすくなります。戦略段階では企業の将来を見据えた方向性や成長機会の整理が行われますが、描かれた構想が実現しなければ想定していた効果にはつながりません。
したがって、戦略策定の完了後にビジネスコンサルティングが実行支援を担い、実務レベルで施策を着実に進めていく体制が求められます。両者が明確に分業するのではなく、段階的に連携して進行していけば、現場の納得感と推進力が生まれやすくなります。
実行フェーズを見据えた設計に基づく戦略と、実現可能性を担保した施策推進の両輪がそろうことで、構想倒れに終わらないプロジェクト運営が可能です。シームレスなバトンリレーを実現する体制づくりがポイントとなるでしょう。
自社にはどちらが必要か?3つの判断ポイント

事業の成長や課題解決のためにコンサルティングの導入を検討する際、事業戦略コンサルティングとビジネスコンサルティングのどちらが自社に適しているか迷うケースは少なくありません。以下では、判断に役立つ3つの視点を提示し、それぞれの観点から検討を深めていきます。
目的・課題の抽出から考える
コンサルティング導入を検討する際、最初に整理すべきなのは自社が抱える課題の種類や到達したい目標の性質です。経営層の間で「中長期的な成長戦略を設計したい」などのニーズがある場合は、事業戦略コンサルティングの活用が効果的です。
将来的なビジネスモデルの再構築や新規事業への投資判断を含む幅広い構想が含まれるため、抽象度の高い議論を受け止める専門的な支援が必要になります。一方、現場レベルでの業務改善や収益向上など、短〜中期での成果を求める局面ではビジネスコンサルティングの支援が適しているでしょう。
例えば営業プロセスの見直しやコスト削減など、現実的な解決策を伴う実行支援が求められる場面にビジネスコンサルティングは適しています。目的を起点とした選定が、プロジェクトの方向性を明確に導きやすくなります。
リソース状況と導入体制の確認
社内での導入体制の整備状況や関与可能なリソースの分布を見直すことも、コンサルティング導入時の判断材料として欠かせません。事業戦略コンサルティングでは経営陣を巻き込むため、長期的な議論を前提としています。経営層が主体的に関与できるかどうかが成果に大きく影響します。
戦略の実現には組織横断的な調整や資源の再配分が必要となる場面が多いため、経営トップの関心や判断の速さも問われるでしょう。対して、ビジネスコンサルティングは実務に直結した改善活動を対象とするため、現場部門の体制や担当者の協力度が進行スピードに直結します。
業務の属人化が進んでいたり、日常業務で多忙な部門が多かったりする場合には、準備期間を設けた上での導入が現実的です。社内のリソース可視化が選択の方向性を定めやすくします。
両方の視点を持ったコンサルタントの選定も効果的
戦略立案と実行支援をそれぞれ別々に依頼する方法もありますが、両面に対応できるコンサルタントを選定する選択肢もあります。近年では、戦略フェーズでの提言に留まらず、実行支援までを一貫して担える体制を整えたコンサルティングファームも増えているのが現状です。
一貫性のあるパートナーを選ぶことで戦略と現場の分断を防ぎ、計画から実装まで一体感を持ったプロジェクト運営が可能になるでしょう。例えば、新規事業構想を立案した後にそのまま業務設計や組織構築までを同じチームが支援することで、移行時の認識ギャップを抑えやすくなります。
また、プロジェクト途中での柔軟な軌道修正や優先順位の再設定にも対応しやすくなるため、環境変化への耐性も高まります。視野の広いパートナー選びが、成果につながる起点となるでしょう。
コンサルティング導入にあたっての注意点

コンサルティング導入は、企業の課題解決や成長を加速させるための有力な手段ですが、成功を収めるためには慎重な計画と実行が求められます。ここでは「費用対効果とROIの測り方」と「プロジェクトの進め方と社内巻き込みのコツ」この2つの観点から導入時の注意点を解説します。
費用対効果とROI(投資利益率)の測り方
コンサルティングサービスの費用は高額になりやすいため、導入時には費用対効果を見極める視点が不可欠です。しかし、単純に「費用が高いから成果も出る」とは限らず、プロジェクトの目的や期待する効果をどれだけ具体的に定義できるかによってその価値が左右されます。
例えば売上向上を狙う場合でも、どの部門にどの程度のインパクトを期待するのかを事前に整理しておくことで成果指標が明確になります。また、KPIの設定や施策ごとのリターン分析を通じて投資対効果の可視化が進むでしょう。
目的の不明確さは、途中での迷走や社内の理解不足を招きやすくなります。金額の大きさではなく、期待成果に対する妥当性や合理性を基に評価軸を設計するのが、納得度の高い意思決定につながるでしょう。
プロジェクトの進め方と社内巻き込みのコツ
コンサルティングの成果は、導入側のスタンスやプロジェクトの進め方によっても大きく左右されます。外部専門家に業務を「依頼」するような受け身の構えでは、期待される成果に届かない可能性が高まります。
自社側の関係者が主体的に関与し、パートナーとして並走する意識を持つことが、現場への浸透や実行定着につながるでしょう。特に現場を巻き込む際にはプロジェクトの背景や目的を丁寧に伝え、当事者意識を育成する取り組みが求められます。
また、社内のキーパーソンを早い段階で巻き込んで推進力のある体制を構築すると、施策の実効性が高まります。コンサルタントとの関係を一方的な指導や指示の関係ではなく、双方向の対話と信頼に基づく「共創」として築く姿勢が、全体の成果を高める要因となるでしょう。
まとめ・競争優位を築くための最適な支援を見極めよう

本記事では、事業戦略コンサルティングの役割と、ビジネスコンサルティングとの違いを解説しました。事業戦略コンサルティングは、市場分析や競合分析に基づいた本質的な戦略策定に特化し企業の長期的な成長を支援します。
一方、ビジネスコンサルティングはより広範な経営課題に対応します。貴社の現状と目的に合わせた最適なコンサルティングを選択したうえで競争優位を確立し、持続的な成長を実現させましょう。
最新の市場動向や効果的な施策が詰まったマーケティング資料を無料でご提供します。ぜひこちらからお申し込みください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





