
夢を形にする羅針盤、それが事業計画です。しかし、多くの事業計画は机上の空論に終わりがちです。成功へのポイントは、事業戦略との連動にあります。 本記事では事業戦略を深く理解し、理解した内容を事業計画に落とし込むための具体的 […]
夢を形にする羅針盤、それが事業計画です。しかし、多くの事業計画は机上の空論に終わりがちです。成功へのポイントは、事業戦略との連動にあります。
本記事では事業戦略を深く理解し、理解した内容を事業計画に落とし込むための具体的なステップを徹底解説します。市場分析から数値計画、リスク管理まで、実現可能性の高い事業計画を作成し、事業を成功へと導くための実践的なノウハウを提供します。
【基礎編】事業計画とは何か?
新たにビジネスを始める場面や、既存の取り組みを拡大させる局面では方向性を定め、行動指針を明確に打ち出す作業は避けて通れません。そこで、求められるのが「事業計画」の策定です。
ここでは、事業計画書の意味と役割を明らかにしたうえで、混同されがちな「事業戦略」との違いや相互の関係性を整理していきます。ビジネスの土台を確実に固めるうえでの第一歩として、基礎的な理解を深めていきましょう。
事業計画書の定義と役割
事業計画書とは、事業の概要・目標・実行手段・収支予測などを網羅的に整理し、文章や数値で体系的に示す資料のことです。事業計画書には、経営者自身の意思を言語化し、全体像を明確に構築する機能があります。
また、社内のメンバーや外部の投資家・金融機関などに対して、将来の展望と実現性を伝えるための根拠資料として活用されます。たとえば、新規ビジネスを立ち上げる際、出資や融資を求める場面で活用されるのが事業計画書です。構想の妥当性と収益の見込みを合理的に示すために、事業計画書の有無と内容が判断材料になります。
内容が具体的で論理的に構成されている資料は、信頼を形成する材料として極めて効果的です。計画を文書化することでアイデアを現実の活動へと橋渡しする働きがあり、ビジネスの出発点として大きな意味を持ちます。
事業戦略との違いと関係性
事業計画と事業戦略は、似た語感を持ちながらも役割が異なります。事業戦略は、競合との比較に基づく立ち位置の分析や、業界内での優位性を築くための方向づけを明示する構想です。対して、事業計画はその構想を実際にどのように展開していくかを具体的に表現する設計図となります。
たとえば、特定のターゲット市場を選定し、価格政策や販路開拓を通じて差別化を図るなどの戦略を立案した場合、戦略内容を日程・人材・予算などの要素に落とし込み、時系列で実行の流れを記述する部分が事業計画です。
戦略が抽象的な「方向性の決定」を担い、計画が「実行プロセスの整理」を担う関係にあり、両者が結びつくことによって初めて実践的な経営活動が成立します。両者を混同せず、連携させて構築する意識が、実行力のあるビジネスを形づくる前提となります。
【準備編】事業計画を成功させる前提条件

実行可能な事業計画を作成するには、事前の土台づくりが欠かせません。具体的な数値やスケジュールを盛り込む以前に、組織としての存在意義や目指す姿を明文化し、外部環境や競合の状況、そして顧客の期待を多角的に把握する作業が必要です。
ここでは、堅実な事業計画を構築するうえで不可欠な要素を段階的に整理し、計画全体の実効性を高めるための準備工程を明らかにしていきます。
ビジョン・ミッション・バリューの明確化
企業や事業が進むべき方向性を明確に描くためには、ビジョン・ミッション・バリューの整備が不可欠です。これらは計画全体の軸を形成し、組織の活動に一貫性をもたらします。ビジョンは将来に描く理想像、ミッションは存在理由、バリューは日々の判断を支える価値観を指します。
たとえば、地域社会への貢献を重視する企業であれば、ビジョンに地域共生の姿を描き、ミッションに地域課題の解決を据え、バリューに共感と誠実さを掲げる形になるでしょう。
明確化するべきことが曖昧である場合、計画全体の方向性がぶれやすくなり、社内外の関係者にも伝わりにくくなります。価値観と理念を起点に計画を組み立てる姿勢が、計画全体に説得力と現実性をもたらします。
市場環境・競合の分析
リスクの低減と機会の最大化を図るには、事業計画を策定するうえで自社を取り巻く外部環境を正確に把握することが欠かせません。また、外部環境分析に加えて事業が属する業界の構造と競争状況、そして競合他社の動向分析も、事業計画の精度を高めるうえで極めて大切です。以下では市場環境と競合の分析を掘り下げました。
外部環境分析(PEST分析)
外部環境の動向を把握する作業は、現実的かつ実行可能な計画を練るうえでの基盤となります。PEST分析では政治・経済・社会・技術、4つの視点から企業活動に影響を与える外的要因を多角的に整理します。たとえば、経済成長の鈍化や人口構造の変化、技術革新の加速などの要素が、事業の展開や市場の選定に大きく関わると覚えておきましょう。
分析した要素を無視した計画は現実との乖離を生み出し、リスクの顕在化を早める要因です。環境の変化に目を向けて影響度の高い要素を見極めたうえで方針を立てることが、将来の展望に整合性と柔軟性を与えるでしょう。
業界・競合分析(5フォース分析、SWOT分析)
業界内での位置づけを見極めて自社の強みを最大化させるためには、競合状況の綿密な把握が欠かせません。5フォース分析では、競争の強さを左右する要因として、新規参入の脅威・買い手と売り手の交渉力・代替品の存在・既存企業間の競争の激しさを可視化します。
また、SWOT分析を通じて自社の内部資源と外部環境を照らし合わせることで、強み・弱み・機会・脅威の関係性を整理できます。たとえば、企業の強みが資金調達力が高いことであれば、新技術導入を進める機会を得やすくなるでしょう。競争構造の理解と、自社の特徴との相互関係の整理によって、効果的な戦術と実現性の高い戦略の設計が可能です。
顧客ニーズの把握
事業活動の根幹を支えるのは、提供する価値が顧客に受け入れられるかどうかで変わってきます。表面的な需要の量ではなく、潜在的な期待や課題に深く踏み込む視点が欠かせません。市場調査やユーザーインタビューなどを通じて、購買行動の動機や選定基準、生活上の不満などを丁寧に収集し分析する姿勢が求められます。
たとえば、利便性を求める層と品質を重視する層では、同じ商品でもアプローチが全く異なります。顧客の行動や感情に基づいた情報を根拠として活用すれば、訴求力の高い施策の立案が可能です。結果として、事業計画が顧客と強く結びついた実践的な内容へと深化していきます。
関連記事:事業戦略スキルとは?必要な能力や立て方・フレームワークを解説!
【実践編・8ステップ】事業計画の主要構成要素とその作り方
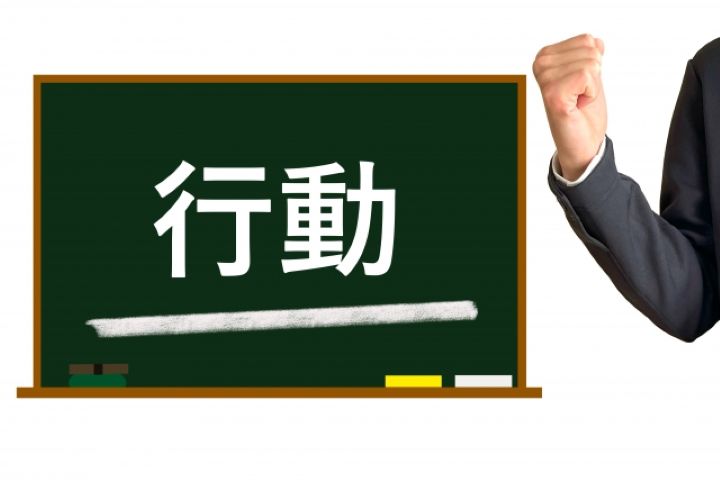
準備段階を経て構想の骨格が定まったあとは、実際に事業計画を構築していく作業が求められます。計画書は単なる報告資料ではなく、事業全体の運営指針を具体化するための設計図です。複数の構成要素が論理的に連結された体制づくりが必要となります。
ここでは、事業概要から財務計画に至るまで、主要構成要素ごとの記述方法と考慮点を丁寧に解説します。ぜひ参考にして、実用性を備えた事業計画書の作成につなげてください。
1. 事業概要の明示
計画全体の冒頭に記載される事業概要は、構想の全体像を簡潔に示す役割を担います。ここの工程では、事業の目的・背景・提供する価値・事業領域を明瞭に記述することが大切です。
たとえば、生活支援サービスを展開する場合には高齢化社会の進行などの背景をもとに、誰に・何を・どう届けるかを明瞭に記すことで、事業の全体像が具体的に浮かび上がります。
事業概要が不明瞭であれば、以降に続く各要素の説得力や一貫性が低下します。冒頭で方向性を明確に示せば計画全体の理解が促進され、信頼性のある構成が実現するでしょう。
2. 市場・顧客分析
事業が展開される市場の特性と、想定される顧客の属性を把握する作業は、提供内容の妥当性を裏付ける役割を果たします。市場規模の推移や成長性、対象とする顧客層の年齢・性別・嗜好などを詳細に分析すると、戦略の方向性が明確になります。
たとえば、20代の女性を主なターゲットとしたアパレル事業を構想する場合、ライフスタイルや消費行動に関するデータをもとに具体性を持たせることが求められるでしょう。市場と顧客の両面から需要を検証すれば、事業構想全体の整合性が高まります。
3. 商品・サービスの提供内容
実際に提供される商品やサービスなどは、特徴・機能・価格帯などを詳細に説明する必要があります。加えて、競合と比較した際の差別化要素や品質・利便性・デザイン性などの訴求点も整理して記述すると良いでしょう。
たとえば、同業他社が提供していないサブスクリプション型の機能を導入している場合、その仕組みや利用者へのメリットを具体的に説明します。商品・サービスの実態が具体性を持って伝わることで顧客に提供される価値が明瞭になり、計画全体の説得力が高まるでしょう。
4. ビジネスモデルの設計
収益の獲得方法を明らかにするビジネスモデルの設計は、事業の実行可能性を示すうえで中核となります。収益の発生源、コスト構造、流通経路、パートナーとの関係などを整理すると、持続的な事業運営が見通せる構造が構築できるでしょう。
たとえば、自社開発のシステムをサブスクリプション形式で提供し、さらに導入サポートを有料で提供することで追加の収益を得るといった場合、このようなビジネスモデルではどこで収益が生まれるのか、どのようにサービスを提供するのかなどモデルの構成要素を整理し、全体像を見える化することが重要です。
全体の構造が明確であれば収益化までの道筋も現実味を帯び、計画に対する信頼性が高まるでしょう。
5. マーケティング戦略
顧客に対して自社の価値をどのように伝え、販売へと結びつけるかを整理するマーケティング戦略では、4P(製品・価格・流通・販促)の各要素をもとに具体的な施策を構築します。ターゲット層の行動傾向や情報接触のチャネルを分析したうえで、広告展開やSNS活用などの方針を策定します。
たとえば、認知度の向上が課題となっている新規ブランドであれば、インフルエンサーとの連携やオンラインイベントの開催など、認知経路を多用することで効果を生み出すでしょう。戦略全体が一貫して顧客との接点を意識して設計されていれば、販売活動の効率が大きく向上します。
6. 組織体制と人材計画
事業を円滑に運営するには必要な職種・人員・スキルを見極めたうえで、組織の構造と人材配置の計画が必要です。起業初期では、少人数で幅広い業務を担う体制が想定される場合が多く、役割分担の明確化がポイントになります。
たとえば、マーケティング・開発・営業を兼任する体制を敷き、外部パートナーと連携する構想がある場合には、その連携方法や契約形態も含めて記載する必要があります。組織の実態と人材戦略を適切に整備すれば、事業の進行に必要なリソースを的確に確保できるでしょう。
7. スケジュール・マイルストーン
事業の進行を計画的に管理するためには、具体的なスケジュールと達成目標(マイルストーン)設定が欠かせません。事業開始から収益化までの期間を見積もり、段階ごとの目標達成基準や行動内容を明記する必要があります。
たとえば、初期3か月でプロダクト開発、6か月でテストマーケティング、9か月で本格展開などの形で、時間軸に沿った工程表の用意が望まれます。進捗の可視化と管理の精度を高めることにより、計画全体に実行性が伴い、外部への説明力も高まるでしょう。
8. 財務計画
事業の経済的な側面を数値で示す財務計画は、事業の実現可能性と収益性を評価するうえで、極めて大切な要素です。また、事業計画を実行するために必要な資金をどのように調達するのか、そして調達した資金をどのように投資していくのかを示す資金調達・投資計画は、事業の持続可能性を確保するうえで欠かせません。
売上・コスト・利益のシミュレーション
事業がもたらす金銭的成果を予測するためには売上見込み、コスト構成、利益水準を数値化しシミュレーションを行う必要があります。収支のバランスや損益分岐点を把握すれば、事業の採算性を客観的に示す資料となるでしょう。
たとえば、月間販売数に対する売上高、原材料費・人件費などの固定費・変動費を細かく設定し、利益率の変動を予測する手法が用いられます。定量的な根拠に基づいた予測を提示すると計画の信頼性が高まり、資金提供者の評価にもつながるでしょう。
資金調達・投資計画
事業開始や拡大に必要な資金の調達方法と、資金の使途に関する明確な設計は財務計画の中核を成します。自己資金・融資・出資などの手段を検討し、それぞれの調達時期・金額・返済方法などの具体化が必要です。
たとえば、初年度に設備投資を集中させる構想がある場合には、投資額と回収見込みの整合性を明記し、過不足なく資金を運用できる設計が求められます。資金繰りの視点を組み込んだ計画が用意されていれば、事業運営の継続性と信頼性を確保できるでしょう。
【発展編】事業戦略と連動した事業計画の立て方

基礎的な計画構成を踏まえたうえで、さらに実効性を高めていくには、長期的な戦略との整合を意識した事業計画の設計が欠かせません。目の前のアクションだけに留まらず、企業としての方向性や将来的な展望と連動した構成を採ることで、短期的な計画が持続性と連携性を持つ内容へと昇華されるでしょう。
ここでは、戦略との接続性を重視しながら、実践的で再現性の高い計画設計の視点を解説します。
中長期戦略との整合性をとる
短期的なアクションを集積しただけの計画では、組織としての発展に結びつきにくくなります。一定期間ごとの目標を設定し、それらが企業の中期・長期の方向性と矛盾なく連動する構成が必要です。
たとえば、5年後に海外展開を見据えている場合には、現地市場の調査や人材育成、パートナーシップ構築などの内容を段階的に組み込んでいく設計が望まれます。各施策が単発で終わらず、将来の成長基盤へとつながるように設計されていれば、経営資源の配分や意思決定の一貫性が確保され、実行性の高い計画へとつながるでしょう。
KPI・OKRの設定による実行管理
計画を単なる理想論に終わらせず具体的な行動として運用するためには、成果の測定基準を明確にしておく必要があります。KPI(重要業績評価指標)やOKR(目標と主要な結果)を設定し、それぞれのタスクやプロジェクトに対して適切な達成基準を与えることによって進捗管理と改善が可能です。
たとえば、月間新規顧客数の増加を目標に掲げる際には、広告経由の問い合わせ件数や成約率などの具体的な数値を指標とし、それぞれの責任者と連動させた運用が必要です。目に見える成果と連動した計画であれば実行段階での行動が曖昧にならず、成果につながる活動が推進されます。
柔軟性を持たせた計画設計
事業環境の変化が速い現在では、一定の柔軟性を計画に組み込むことが不可欠です。初期の想定どおりにすべてが進行するとは限らず、外部要因や内部事情の変動により、当初の計画を調整する場面が頻繁に生じます。想定外の変動に対応するには、代替案や選択肢をあらかじめ構築しておくことが必要です。
たとえば、主力商品の売上が想定を下回った場合には、販路の切り替えやキャンペーン施策の強化など、複数の手段を想定しておく設計が現実的です。柔軟性のある構造であれば、予期せぬ状況でも軌道修正が可能となり、持続的な運営が可能となるでしょう。
関連記事:事業戦略の立て方を紹介!策定の6つのポイントと手順を徹底解説
【注意点】失敗しやすい事業計画のパターン

計画の構築時に見落とされやすい視点や、甘さの残る数値設定、顧客視点の欠如などが重なると、期待していた成果には至りません。ここでは、つまずきやすい典型的なパターンと、計画の修正・改善に向けた視点などを掘り下げていきます。
よくある落とし穴|数字の裏付け・顧客視点・売上見込み
事業計画を構築する際に頻出する失敗の一つが、具体的な数値根拠の欠如や顧客視点の不足に起因する構造の弱さです。売上や利益の予測に対して明確な根拠がなく、過去のデータや市場調査に基づかない推測に近い数値を記載してしまうと、信頼性に乏しい資料となるでしょう。
また、提供する商品やサービスの価値を発信する際に企業側の都合に偏り、顧客にとっての利便性や魅力を欠いた内容になっている場合も多く見られます。さらに、売上の予測に関しては、潜在顧客数や成約率、単価などの要素を正確に積み上げていないと実現性の低い計画となり、実行段階での資金繰りに影響が及びます。
こうした構成の欠点が重なった計画では事業自体の信頼性が損なわれ、出資や支援を得にくくなるでしょう。
修正・改善のポイント
計画段階での誤りや弱点を放置すれば、実行後のトラブルや進行の遅れにつながるため、構成の見直しと再設計が必要です。まず着手すべき点は、計画に記載した数値や根拠を再点検して外部データや統計情報との整合を取る作業です。
数字の根拠が曖昧である場合には業界レポートや競合分析を参照し、可能な範囲で第三者が納得できる裏付けを加えていきます。また、顧客ニーズへの理解が不十分な場合には、アンケートやインタビューなどを通じて一次情報を収集し、サービス内容と照らし合わせた見直しを行いましょう。
さらに、売上見込みが過大である場合にはシミュレーションを複数パターン用意し、現実的な数字を軸とした設計に切り替える必要があります。これらの視点を取り入れた修正によって、計画は再現性と説得力を高めた内容へと発展していくでしょう。
まとめ・事業計画は生きたドキュメント

本記事では、事業戦略を核とした成功する事業計画の立て方を解説しました。大切なのは、戦略と計画を一貫させ、市場の変化に柔軟に対応できる体制の構築です。
今回紹介したステップとポイントを参考に実現可能性の高い事業計画を作成し、着実に事業を推進していきましょう。事業計画は一度作ったら終わりではありません。定期的な見直しと改善を行いながら、事業をさらなる成長へと導いてください。
実践的なマーケティング計画の策定に役立つ情報満載の資料をご希望の方は、こちらからご請求ください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





