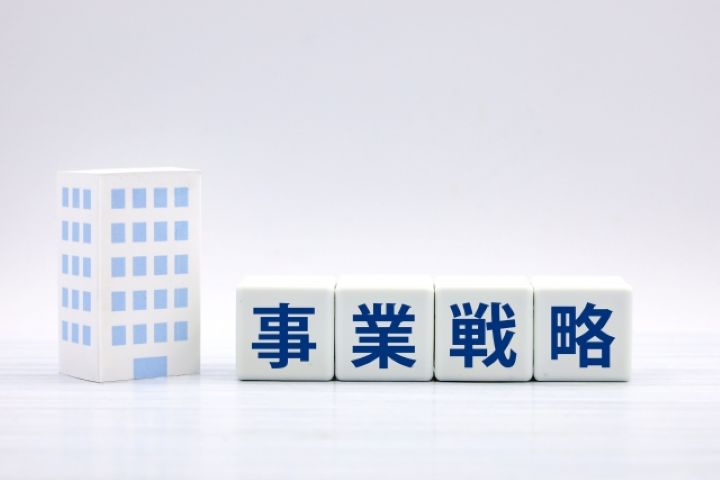
「事業戦略」と「戦術」はビジネスの現場でよく耳にする言葉ですが、両者の違いを明確に理解できていますか?本記事では、事業を成功に導くための羅針盤となる事業戦略と、それを実現するための具体的な行動計画である戦術を基本からわか […]
「事業戦略」と「戦術」はビジネスの現場でよく耳にする言葉ですが、両者の違いを明確に理解できていますか?本記事では、事業を成功に導くための羅針盤となる事業戦略と、それを実現するための具体的な行動計画である戦術を基本からわかりやすく解説します。
自身のビジネスに適切な選択をするためにぜひお読みください。そして、両者の関係性を理解し、効果的な事業運営に繋げるための第一歩を踏み出しましょう。
事業戦略とは何か?
企業の持続的な成長と競争優位の確立に「事業戦略」は欠かせません。ここでは、戦略の定義、戦略の目的や役割、そして具体例までを通して事業戦略の基本的な理解を深めていきます。
戦略の基本的な定義
戦略とは、組織が将来的に目指す姿を実現するために限られた経営資源をいかに効果的に配分し、持続的な成果を導くかを体系的に考える枠組みのことです。単なる計画や目標とは異なり、外部環境の変化や競合他社の動向を考慮したうえで、競争優位を築くための指針として設計されます。
戦略の概念に基づく思考は短期的な視点に留まらず、中長期的な視野に立って方向性を明確に打ち出します。たとえば、市場でのポジショニングを見極めたうえで、製品開発や販売チャネルを選定するプロセスも戦略の一部です。全体として、戦略は組織全体を牽引するための地図のような役割を果たします。
戦略の目的と役割
戦略の本質的な目的は、企業が保有するリソースを最も効果的に活用し、目指す成果を効率的に実現するための道筋を明確にする点です。経営環境が複雑化し不確実性が高まる現代では、場当たり的な対応ではなく、長期的な視野に基づいた方向性の提示が求められます。戦略は組織全体の判断基準となり、意思決定や行動の一貫性を生み出す役割を担う存在です。
たとえば、成長市場への集中投資を通じて収益性を高めるために、既存事業の再構築を進める施策も戦略的な選択に含まれます。こうした一連の方針が明確であるほど、組織は自信を持って行動に移しやすくなるはずです。戦略は、企業が変化に柔軟に対応しながらも軸を失わずに前進していくための羅針盤としての役割を果たします。
戦略の具体例
戦略の実践的な内容は企業によって異なりますが、共通しているのは経営目標の達成に向けて一貫した方針のもとで意思決定を行うことです。
たとえば、国内市場が成熟した環境下で、ある企業が成長機会を求めて海外展開を加速させるケースがあります。そうした際には、対象とする国や地域の市場特性を分析し、製品ラインナップや価格設定、現地パートナーとの提携方法までの総合的な設計が戦略として求められるでしょう。
さらに、同業他社との差別化を意識したブランド戦略の構築や、デジタル技術を活用した新たな販売モデルの導入も、競争力を高めるための選択肢となります。戦略は単なる目標設定ではなく、現実的かつ多角的な視点で経営資源を再構築していく取り組みとして具体化されていきます。
事業に対する戦術とは何か?
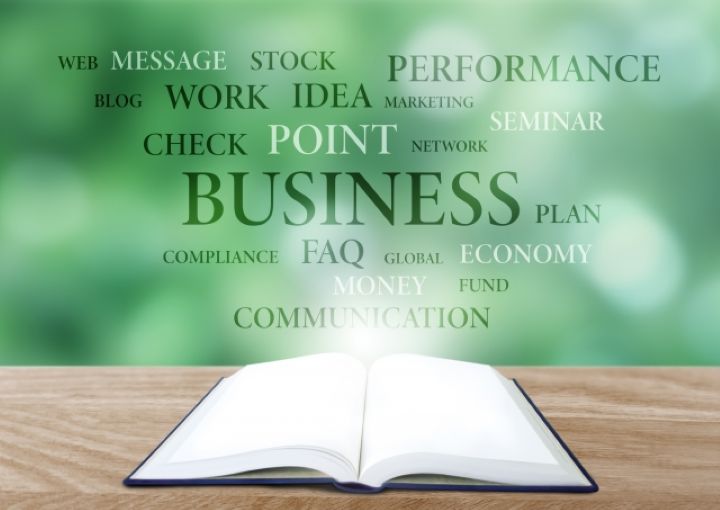
企業活動を着実に前進させるためには、長期的な視野に基づいた事業戦略だけでなく、現場レベルで具体的な行動を導く戦術が必要です。ここでは、戦術の定義や目的、役割、さらには具体的な内容に至るまで、実務に即した視点で解説します。
戦術の基本的な定義
戦術は、組織が掲げる戦略を実現へ導くために、現場レベルで採用される具体的な手段や施策を指します。経営層が定めた中長期的な方向性を実際の業務に落とし込むには、具体的な戦術的視点が欠かせません。戦略が全体の地図であるなら、戦術は戦略が生んだルートを実際に進むための具体的な手配や動きにあたります。
具体的には、販売拡大を目標とする戦略に対し、個別店舗でのキャンペーン設計や営業チームの行動計画を設ける対応が戦術に該当します。戦術は方針を実践的な段階に移す際に欠かせない構成要素であり、計画と実行を橋渡しする役目を果たす大切なものです。
戦術の目的と役割
戦術の目的は、設定された戦略を具体的かつ実行可能な形へと変換し、組織全体で着実な成果を生み出す体制を構築することです。抽象的な方向性だけでは行動が伴わず、成果にも結びつきにくいため、各部門やチームに適した施策を明文化し、日常業務に反映させることが必要です。戦術は戦略の実効性を高め、組織の足並みをそろえる仕組みとして機能します。
新商品を短期間で市場に浸透させる場合、ターゲット層への的確な訴求手段や広告展開のタイミングなど、個別の戦術が成果に直結します。全体を統一する方針があった場合、実行段階での工夫と緻密な対応が伴わなければ、期待された結果は得られません。期待される結果を実現するために、戦術は現場主導で成果を生み出す推進力として位置づけられます。
戦術の具体例
戦術は業種や業態によって多様な形を取りますが、共通するのは実行を前提とした具体的な施策である点です。たとえば、小売業では季節商品を強化する戦略がある場合、戦術としてはディスプレイの変更、スタッフへの販売トーク共有、SNSを活用した情報発信の強化などが挙げられます。
これらの手段は、現場が迅速に動きやすくなるよう具体性を持たせる必要があります。また、営業部門では成約率の向上を狙う場合には、訪問件数の設定、提案資料の最適化、商談の進め方に関するトレーニング導入などの戦術が効果的です。
このような取り組みを通じて、戦略が意図する方向へと業績を導く役割が期待されます。戦術は単なる作業手順ではなく、戦略との整合性を保ちつつ、実行面での完成度を高める設計です。
関連記事:事業戦略の構成要素とは?フレームワークや計画の立て方も解説!
事業戦略と戦術の違いとは?

企業経営を取り巻く環境が複雑さを増す中で、長期的な方向性を示す事業戦略と、具体的な施策に落とし込む戦術の両方を理解し、適切に使い分ける姿勢が求められています。ここでは、それぞれの特徴を明らかにしながら事業運営で実践的な理解を深めていきましょう。
視点・スコープの違い
事業戦略と戦術は、扱う視点や対象範囲で明確な差があります。事業戦略は、経営全体の方向性を設計する上位概念であり、中長期的な未来を見据えた構想を担うのが特徴です。一方、戦術は方針を現場で実行に移すための短期的かつ限定的な取り組みに焦点を当てるのが特徴です。
戦略では市場の動向、競合状況、自社の強み・弱みなどを包括的に捉える必要があり、視野の広さと持続的な成果を導く構造が求められます。対して戦術は、特定の業務や活動に対してより詳細かつ具体的な対応を設計し、日々の実行力に直結する側面が強くなります。時間軸や関与する範囲の広さを見ると、戦略と戦術は役割の違いが明確です。
目的と対象の違い
戦略と戦術では、目指す成果と対象範囲が異なります。戦略の目的は、組織全体の成長や持続的な競争優位の構築です。さらに、経営資源をどの方向に集中させるかを明確にする役割があります。対象としては、企業全体や複数の事業領域など広範囲にわたる計画を伴います。
一方、戦術は設定された目標の実現に向け、個々の業務や活動単位での実行計画を具体化する役目を担う存在です。対象となるのは部署単位、プロジェクト単位など限定的な範囲であり、現場が動きやすくなるように構成されます。目指す地点と到達手段の違いは、戦略は道筋の設定、戦術は道筋を進むための行動設計として覚えておくと分かりやすいでしょう。
関わる人の違い
関わる人材の層に明確な差があるのが事業戦略と戦術の特徴の一つです。戦略を構築する段階では経営者層や役員クラスが中心となり、企業全体の方向性を見据えた意思決定が求められます。組織の長期的ビジョンや資源配分、競争環境の分析など高度な思考と広範な視野が必要です。
一方で戦術の設計や実行には、ミドルマネジメント層や現場の実務担当者が深く関与します。戦略に基づいた行動計画を具体的に設計しチームを動かしていくためには、実務に精通した人材の知見や経験の反映が必要です。関与する人材の役割や位置づけが異なるため、両者は互いに連携しつつも異なる次元で意思決定を行っています。
意志決定と柔軟性
戦略と戦術では、意思決定の性質や柔軟性に違いが見られます。戦略は中長期的な視点で構築されるため、一度定めると容易には変更できません。全社的な方向性や経営リソースの配分にかかわるため、変更には大きな影響を伴います。したがって、意思決定には時間をかけて慎重に検討する必要があり、変更のタイミングも限られる傾向があるでしょう。
一方、戦術は環境や状況に応じて柔軟に修正しやすい性質を持ちます。実行段階で成果が得られないと判断されれば迅速に見直しを行い、別のアプローチへ移行する対応も可能です。こうした柔軟性により、戦術は現場での適応力を高め、戦略との整合性を保ちながら臨機応変に動ける実践的な要素となります。
戦略と戦術の関係性

企業活動では戦略と戦術はそれぞれ独立した概念ではなく、相互に補完し合う関係にあります。戦略が全体の方向性や大枠を示す構想である一方、戦術は戦略構想を現場レベルで実現へ導く実践的な手段です。
両者は単に並列的に存在するのではなく、戦略があって初めて戦術が機能し、戦術が適切に運用されなければ成果に結びつきません。両者の関係性を正確に理解すれば、組織は効率的かつ効果的に目標達成を目指せるでしょう。
戦略なくして戦術は成り立たない
戦術は、明確な戦略のもと構築されるため、戦略が不在の状態では方向性を欠いた施策の羅列に陥ります。現場での具体的な行動を積み重ねるだけでは、企業全体が目指す目的地に近づく保証はありません。戦略が描くビジョンや目標をもとに設計されることで、戦術は効果的に機能し始めます。
たとえば、収益構造の転換を意図した戦略が定まっていれば、それに沿った価格体系の見直しや販売方法の選定など、現場での判断にも統一性が生まれます。土台となる戦略が定まっていなければ、戦術は散発的な対応に留まり、継続的な成果を期待できません。戦術の精度や一貫性を高めるためには、戦略によって大きな流れを明示しておく必要があります。
戦略を実行可能にするのが戦術の役割
戦略は構想段階で抽象的な要素を含みますが、それだけでは成果につながりません。戦略を現実にトップダウンし、具体的な行動へと変換する役割を担うのが戦術です。戦術の設計には、現場で活用可能なレベルまで内容を落とし込み、関係者全体に共通の認識として浸透させる工夫が求められます。
たとえば、デジタル領域での顧客接点強化を図る戦略が掲げられている場合には、SNS運用の体制整備や発信タイミングの調整、分析ツールの導入など個別の戦術を具体的に整えていくことが欠かせません。
以上のような戦術が段階的かつ連動的に実施されることで、抽象的だった戦略が明確な成果として形を成します。つまり、戦術は戦略を現場へとつなぎ、実現性を高めるための橋渡しの役割を果たしています。
戦略と戦術が噛み合わないとどうなるか?

全体像を描いた戦略と、現場での実行を担う戦術がかみ合わなければ、組織全体に混乱が広がって持続的な成長も期待できません。ここでは、戦略と戦術の不一致が招くリスクや失敗例、さらに回避に向けた具体的な視点を整理していきます。
ありがちな失敗例
戦略と戦術が乖離した状況では現場での行動が方向性を見失い、施策が効果を発揮しないまま終わる傾向が見られます。戦略レベルで掲げた目標と実際に展開されている施策の間に整合性がなければ、組織全体の動きが分散しやすくなり意図された成果を導けません。
たとえば、顧客基盤の拡大を目指す戦略が策定されたにもかかわらず、現場では既存顧客への対応強化にばかり注力している場合、リソース配分のズレが成果を妨げるでしょう。
また、現場からのフィードバックを十分に吸い上げないまま戦術を固定化すると、時流に合わない施策が繰り返される恐れもあります。こうした構図では、目標達成への道筋が不透明となり、信頼やモチベーションの低下を招く恐れがあります。
失敗を防ぐ方法
戦略と戦術を一致させるためには、両者の接続点を常に可視化しながら、上層と現場の間に継続的な対話を生み出す体制が求められます。戦略を掲げるだけでは足りず、それが現場でどのように形になり、どのように進行しているかを適切に把握できる仕組みが欠かせません。
失敗を防ぐためには、戦略立案段階から現場の視点を踏まえた設計を行い、戦術の柔軟な修正が可能な状態を維持することが効果的です。たとえば、定期的な部門横断ミーティングを設けて、現場の進捗や課題を戦略レベルで共有することでズレを早期に発見し、修正が可能になるでしょう。
また、目標の可視化やKPIの整備によって戦略と戦術の関連性が一貫した形で維持され、組織全体の動きにも統一感が生まれます。こうした体制整備によって、戦略と戦術の分断を回避し、実行力を高める道筋が見えてきます。
関連記事:事業戦略の成功事例を紹介!策定する際の5つのポイントも徹底解説
事例で理解する!戦略と戦術の使い分け

ここでは、実際の業種での取り組みを例に、戦略と戦術の役割や具体的な分岐点を整理していきます。
事例1・飲食チェーンの新規出店戦略
ある飲食チェーンは、中期的な成長を見据えて出店エリアの拡大に注力しました。経営陣が掲げた方針は「都市部以外の生活密着型エリアへと販路を広げ、地域密着型ブランドとしての認知を高める」ことでした。
経営陣が示す方向性は明確な戦略として位置づけられ、企業全体の価値を高める構想として機能しています。経営陣の戦略に対して、具体的な店舗配置の選定や物件交渉、地域別のメニュー開発、スタッフ採用などの一連の活動が戦術にあたります。また、各エリアごとに導入された販促ツールや、開店時期の調整なども戦術として実行されました。
以上のように、企業の未来を見据えた大枠が戦略であり、戦略を日常の実務に展開した行動群が戦術です。両者を適切に連動させる設計によって現場が自律的に動き、出店ごとの成果が積み上がる構図が築かれています。
事例2・SaaS企業の成長モデル
あるSaaS系企業では継続的な成長を実現するために、導入後の顧客維持率を最大化する方向へと経営資源を集中させました。経営資源を集中させた方針は既存顧客のロイヤリティを強化し、解約率を抑えることで長期収益を安定させる構造をつくる狙いを含んでいます。こうした構想が戦略として策定され、長期的な利益構造を支える核となりました。
そして、戦略の実現に向けて行われた取り組みには、カスタマーサクセス部門の増員やサポート体制の強化、オンボーディング支援の再設計、定期的なユーザーインタビューの導入などが含まれます。これらの施策が、戦術として実施されました。
戦略の方向性に沿って戦術が現場で具体的に実行され、顧客との継続的な関係が維持されています。構想から実行までを段階的に紐づけることで、全社的な成長モデルとしての安定性が確保されました。
自社での使い分けのポイント

ここでは、自社で戦略と戦術を適切に使い分けるために、戦略立案時と戦術設計時のそれぞれで特に意識すべきポイントを解説します。
戦略立案時に意識すべきこと
戦略を立案する段階では事業全体が進むべき方向を明示し、長期的な視点での価値創出を目指す構図が求められます。戦略を立案する際、現時点の課題や業界の流れだけに着目すると、変化に対応しにくい構想に陥る可能性が高いです。
自社が持つ経営資源、社会環境、市場の動向、競合の状況などを総合的に踏まえ、どの領域で競争優位を発揮できるのか、そしてどこに経営資源を集中すべきかを見極める視点が欠かせません。
特に新規市場への進出を検討する場合には、その市場が自社の強みとどのように結びつくかを分析し、自社が提供できる価値を明確にすることが大切です。さらに、その価値が既存の収益構造やブランド戦略と整合性が取れているかどうかも含めて、慎重に検討を行う必要があります。
戦略は抽象度の高い構想であるため関係者の認識がばらつかないよう、設計段階から共通理解を意識する視点が求められます。
戦術設計時に意識すべきこと
戦術設計は、掲げられた戦略の方向性を現場の実務に落とし込み、実行可能な形への転換が欠かせません。戦術設計の際に焦点を当てるべきは、具体性と柔軟性の両立です。
目指す成果に直結する動きを構築するためには、目標数値の設定や行動手順を明確化するだけでなく、関係部署間の連携を滑らかに保つ運用体制の構築も必要です。たとえば、販売促進を目的としたキャンペーンを展開する場合、企画内容に加えて顧客導線、媒体の選定、配信タイミング、効果測定の流れまでを具体的に整えておく必要があります。
また、想定外の状況に対応できるよう、見直し可能な設計としておく姿勢も成果に直結します。戦術は実行に関わる人員の理解と共感が大きな影響を与えるため、現場の声を反映しながら柔軟な運用設計を行う視点が求められると覚えておきましょう。
戦略と戦術を正しく機能させるための仕組み

ここでは、戦略を組織全体に浸透させるための施策と、PDCAサイクルと連動させた効果的な戦術運用を解説します。
戦略の浸透施策
策定された戦略が社内に定着し、意図した方向に行動が統一されるためには、段階的な浸透施策の設計が求められます。まず必要となるのが、戦略を抽象的な理念に留めず、具体的な方向や目指す状態を言語化し、各部門や職種に適した形で伝える工夫です。
戦略が策定されたうえで単なる情報共有ではなく、理解と納得を促す対話の場を設けることで、現場の解釈にズレが生じにくくなります。たとえば、経営陣による説明会やミドル層とのディスカッション、マネジメント層を対象としたワークショップの実施が挙げられます。
さらに、評価指標や目標設定の仕組みに戦略の要素を組み込むことで、日常業務との関連を可視化するのが効果的です。継続的なフィードバック機会や情報更新の体制もあわせて整えることで、戦略が静的な文書に留まらず、動的に機能する状態へと変化していくでしょう。
PDCAと連動させた戦術運用
戦術の運用では、定めた方針をただ実行に移すだけでなく、戦術の効果や課題を常に確認しながら調整を重ねる体制づくりが欠かせません。特に、PDCAのフレームと連動させた設計により、現場が自律的に動きながらも戦略の方向と連動した運用の実現が可能です。
PDCAサイクルとは、継続的な業務改善を行うためのフレームワークです。以下の4つのステップで構成されます。
Plan(計画)
- 目標を設定し、達成するための計画を立てる
- 現状分析を行い、課題を明確にする
- 改善策やアクションプランを策定する
Do(実行)
- 計画した内容を実際に実行する
- 必要なリソースを活用し、業務プロセスを進める
- 実施結果を記録し、データを蓄積する
Check(評価)
- 実施した結果を分析し、計画通りに進んでいるかを確認する
- 達成度を測定し、問題点を特定する
- 改善が必要な点を明らかにする
Act(改善)
- 評価結果をもとに改善策を実行し、業務プロセスを修正する
- 必要に応じて新たな計画を立て、次のPDCAサイクルに活かす
- 継続的な改善を行い、品質や業務効率を向上させる
具体的には、まず施策ごとの目標や期待される成果を設定し、設定した内容に沿った行動計画を明確にします。次に、実施段階では数値や定性的なデータを蓄積し、関係部署と共有可能な状態で可視化します。検証の場では、実績に対する評価と成果の背景分析を丁寧に行い、次の展開へ反映させる設計を構築しましょう。
こうした一連の流れを定期的なリズムで実施すれば施策が一過性で終わらず、組織全体としての習熟度も高まっていきます。結果として、戦略の実現可能性が高まり、再現性のある実行体制が築かれます。
まとめ・戦略と戦術の違いを明確にし、ビジネスを成功させよう
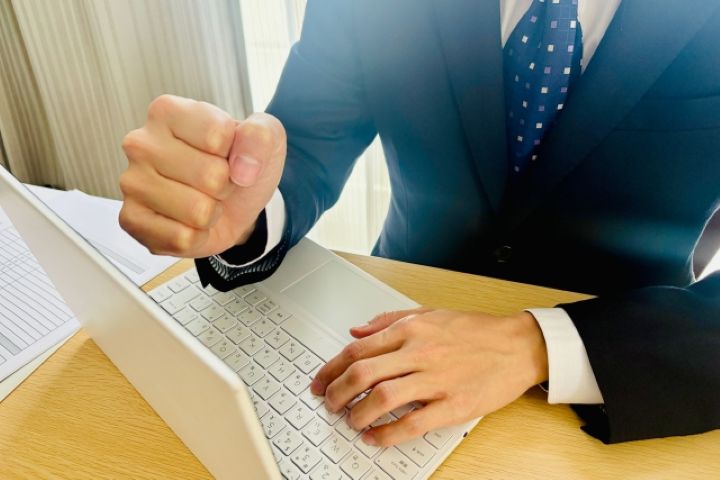
事業戦略は長期的な目標達成に向けた全体像を描き、戦術は戦略を実行するための具体的な手段になります。両者は車の両輪のような存在です。どちらかが欠けたら事業は円滑に進みません。本記事で解説した基本を理解し、自社の事業戦略と戦術を改めて見直すことで、変化の激しい現代でも持続的な成長を実現できるはずです。
マーケティング戦略を加速させるヒントが満載の資料が必要な場合は、ぜひこちらにお問い合わせください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





