
財務分析は、企業の経営状況を把握し、戦略的な意思決定を行うために欠かせない手法です。収益性や安全性、成長性などの視点から分析することで、企業の強みや課題が浮き彫りになります。 しかし、分析作業は専門的な知識や時間を要する […]
財務分析は、企業の経営状況を把握し、戦略的な意思決定を行うために欠かせない手法です。収益性や安全性、成長性などの視点から分析することで、企業の強みや課題が浮き彫りになります。
しかし、分析作業は専門的な知識や時間を要するため、多くの経営者にとってハードルが高いのも事実です。本記事では、財務分析の基本から具体的な手法、テンプレート作成に役立つツールや無料サービスまでを詳しく解説し、初心者でも取り組みやすい方法を提案します。
財務分析とは?

財務分析とは、企業の財政状況や経営成績を把握し、現状の強みや課題を明確化するための手法です。主に経営者、投資家、金融機関などのステークホルダーが利用します。これにより、経営戦略の策定や資金調達の判断、投資の適否評価が可能になります。
財務分析の中心となるのは、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表のデータです。これらを基に企業の収益性や安全性、効率性などを評価し、課題解決や成長戦略の策定に役立てます。たとえば、売上高や純利益の増減を分析することで収益構造を把握したり、負債比率や自己資本比率を通じて財務の健全性を評価したりします。
また、財務分析は単に過去の実績を振り返るだけではなく、将来の経営リスクや成長可能性を見通す大切な役割も果たします。そのため、適切な分析手法や指標の選択が成功のポイントとなります。
財務分析テンプレート作成のための必要書類
財務分析テンプレートを作成するには、企業の経営状況を正確に把握できる財務諸表を揃える必要があります。主に用いられるのは、貸借対照表と損益計算書です。これらの書類を正しく活用することで、財務分析の基盤を整えることができます。
貸借対照表
貸借対照表は、企業の財政状態を示す大切な資料です。特定時点の資産、負債、純資産の状況が記載され、企業がどれだけの価値を保有しているか、またどれだけの義務を負っているかを明らかにします。資産は現金や設備、売掛金などの項目で構成され、負債には借入金や買掛金などが含まれます。
これらの差額に当たる純資産は、企業の財務基盤の健全性を評価する上で特に注目される指標です。たとえば、自己資本比率が高い場合、借入に依存しない健全な経営が行われていることを示します。
損益計算書
損益計算書は、企業の一定期間の収益と費用の動きを示す書類です。売上高や営業利益、経常利益、純利益などの項目が記載されており、それぞれの数値を分析することで収益構造の特徴を把握することができます。
営業利益は本業の収益性を測るために欠かせない指標で、経営戦略の成果を判断する際に役立ちます。一方、純利益は、収益力や企業の成長可能性を評価する際の最終的な指標として用いられます。
計算書の見方・読み方
財務諸表を正しく読み解く能力も大切です。貸借対照表では、資産と負債のバランスを注視する必要があります。たとえば、自己資本比率が高い企業は、外部からの借入に依存せず、強固な財務基盤を持っていると評価されます。
一方、損益計算書では、売上高や利益率の推移を確認し、経営成果を数値として捉えることが欠かせません。また、流動比率や総資産回転率などの指標を算出し、業界平均や過去データと比較することで、経営パフォーマンスを客観的に評価することが可能になります。
財務分析の5つの手法

財務分析では、企業の経営状態を多角的に評価するためにさまざまな手法が用いられます。特に「収益性分析」「安全性分析」「生産性分析」「効率性分析」「成長性分析」の5つが主要なアプローチとして知られています。それぞれの手法を詳しく見ていきましょう。
①収益性分析
収益性分析は、企業がどれだけ効率よく利益を生み出しているかを評価する手法です。この分析では、売上高や総資産、自己資本などに対する利益の比率が大切な指標となります。たとえば、売上高営業利益率は本業の収益性を測るための基本的な指標であり、企業の競争力を示す一つの尺度です。
また、自己資本利益率(ROE)は、株主から預かった資本をどれだけ効果的に活用しているかを評価するのに用いられます。
収益性分析の結果は、企業の利益構造を改善するための方針策定に直結します。利益率が低い場合は、コスト削減や価格設定の見直しなどの施策を検討するきっかけとなります。
②安全性分析
安全性分析は、企業が持続的に事業を運営するための安定性を評価する手法です。この分析では、負債比率や流動比率などの指標が注目されます。負債比率が高い場合、企業の財務構造が不安定である可能性が指摘される一方、流動比率が高い場合には短期的な支払い能力が十分であると判断されます。
特に借入金依存度や自己資本比率は、外部から資金を調達する際の大切な評価基準となります。これらの指標を活用することで、経営者はリスク管理の観点から健全な財務政策を策定することが可能になります。
③生産性分析
生産性分析は、企業が持つリソースをどれだけ効率的に活用しているかを評価します。この手法では、従業員一人あたりの売上高や利益などの指標が使われます。たとえば、労働生産性を測ることで、業務プロセスや従業員のパフォーマンスを数値化することができます。
この分析結果は、業務の効率化や従業員教育の見直しを行う際の指針となります。生産性が向上することで、収益性や競争力の向上にもつながります。
④効率性分析
効率性分析は、資産や負債の活用度を評価するための手法です。総資産回転率や売上債権回転率などが主な指標として用いられます。これらの指標を通じて、企業がどれだけ効率的に資産を活用して売上を上げているかを把握できます。
たとえば、総資産回転率が高い場合、企業は効率的に資産を運用していると判断できます。一方で、回転率が低い場合は、余剰な資産や改善の余地がある運用方法が示唆されます。この分析を通じて、資本配分の適正化や不良資産の削減などの戦略を立案することが可能です。
⑤成長性分析
成長性分析は、企業が将来的にどれだけ事業を拡大できるかを評価する手法です。売上高成長率や利益成長率などの指標を用い、過去の実績や業界全体の動向と比較して、企業の成長ポテンシャルを測定します。
この分析は、特に新興企業やベンチャー企業の評価で大切です。成長性が高い企業は投資家から注目されやすく、資金調達や市場シェアの拡大に有利となります。一方で、成長率が低下している場合には、新たな事業領域の模索や収益構造の見直しが求められます。
財務分析のテンプレートを作るのに適したツール

財務分析テンプレートを作成する際には、データの整理や視覚化が簡単に行えるツールを利用すると効率的です。ここでは、財務分析のテンプレート作成に適した主要なツールとして、Excel、Googleスプレッドシート、Notionの3つを取り上げ、それぞれの特徴や操作感を解説します。
Excel
Microsoft Excelは、財務分析に最適なツールとして広く利用されています。Excelの強みは、柔軟性と高度な機能性にあります。膨大なデータを扱うことが可能で、関数やマクロを活用することで、複雑な計算や自動化も容易に実現できます。
また、ピボットテーブルやグラフ作成機能を用いることで、データを視覚化し、分析結果をわかりやすく提示することができます。
特に財務分析テンプレートを構築する際には、収益性や安全性の指標を算出するための計算式を簡単に組み込むことができます。また、複数のシートを連動させることで、異なる期間や部門ごとのデータを一括管理できる点もExcelの魅力です。一方で、操作がやや複雑なため、初心者には一定の学習が必要になる場合があります。
Googleスプレッドシート
Googleスプレッドシートは、クラウドベースで利用できるため、複数人での共同作業やリアルタイムでの更新が必要な場面に適しています。Excelと同様に多くの関数やグラフ作成機能を備えていますが、操作感がシンプルで、初心者でも直感的に扱えるのが特徴です。
特にインターネット接続環境が整っていれば、場所やデバイスを選ばず作業ができるため、リモートワークや多拠点での業務に適しています。また、スプレッドシート内でGoogle Apps Scriptを利用すれば、カスタム機能を追加して分析業務を効率化することも可能です。
制約としては、Excelに比べて高度な機能や大規模データの処理には向かない点があります。
Notion
Notionは、メモやプロジェクト管理、データベース管理など多機能なプラットフォームとして知られていますが、財務分析テンプレートの作成にも利用可能です。Notionの強みは、データベース機能とカスタマイズ性の高さにあります。必要な指標や項目を自由にレイアウトし、財務データを整理するのに便利です。
また、分析結果をドキュメント内に直接記録したり、チームメンバーと共有したりすることも簡単です。シンプルな表やグラフを作成するのに適しており、視覚的にもわかりやすいデザインを維持しながら財務分析を行えます。ただし、Notionは大規模なデータ処理や高度な数式の計算には向かないため、シンプルなテンプレート作成に適したツールです。
財務分析のテンプレートの無料ツール4選
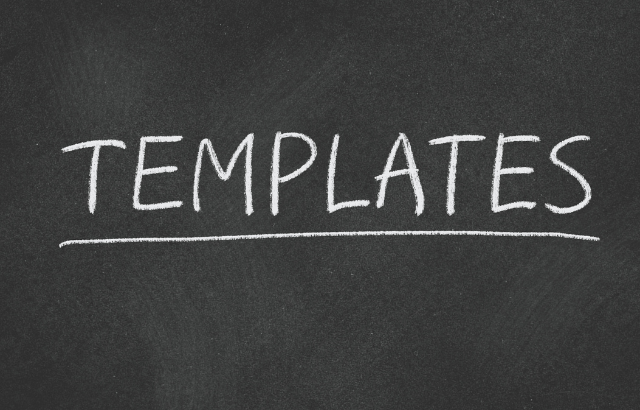
財務分析を効率的に進めるためには、無料で使える便利なツールを活用するのも効果的です。ここでは、日本国内で利用できる財務分析に特化した無料ツールを4つ紹介します。それぞれの特徴や使い勝手を具体的に解説します。
①日本金融公庫「財務診断サービス」
日本金融公庫が提供する「財務診断サービス」は、中小企業向けに設計された無料の財務分析ツールです。企業が提出した財務諸表を基に、収益性や安全性、成長性などの財務指標を自動で算出し、診断結果をレポート形式で提供します。このサービスは、特に初めて財務分析を行う方にも使いやすい設計となっており、結果の解釈がしやすい点が大きな特徴です。
また、分析結果はグラフや表で視覚的に表示されるため、企業の財務状態を直感的に理解できます。中小企業の経営者や担当者が、経営改善のヒントを得るために活用するのに最適なツールです。
②J-Net21「経営自己判断システム」
J-Net21が提供する「経営自己判断システム」は、中小企業庁が支援するサービスで、経営状態を自己診断するためのツールです。このシステムでは、貸借対照表や損益計算書のデータを入力するだけで、収益性や安全性のほか、効率性や成長性も診断が行えます。
このツールの大きな魅力は、診断結果に基づいて具体的な改善案を提案してくれる点にあります。また、業種や地域別の平均値と比較することで、自社の立ち位置を把握することが可能です。操作もとても簡単で、専門知識がなくても利用できるため、多くの中小企業に支持されています。
③経済産業省「ローカルベンチマーク」
経済産業省が提供する「ローカルベンチマーク」は、財務データを活用して企業の成長可能性や経営課題を分析するためのツールです。特徴として、財務データだけでなく、非財務データ(企業文化や地域貢献など)も考慮した総合的な診断が行える点が挙げられます。
このツールは、診断結果を基に、金融機関や専門家と共有することが推奨されており、外部支援を受ける際の資料としても活用されています。また、無料で提供されるガイドラインに従うことで、経営者自身が簡単に財務分析を進めることができます。
④上原会計事務所「会社の健康診断」
税理士法人上原会計事務所が提供する「会社の健康診断」は、簡単に自社の財務状況を分析できる無料ツールです。このツールでは、財務データを入力すると、企業の安全性や収益性をグラフ化し、わかりやすいレポートを作成してくれます。特に、視覚的なわかりやすさに重点を置いており、経営状況を直感的に把握できるのが特徴です。
このサービスは、財務分析を初めて行う企業にとって有用であり、専門的な知識がなくても簡単に利用できます。また、診断結果を基に税理士事務所に相談することで、さらに具体的なアドバイスを受けることが可能です。
まとめ
財務分析は、企業の現状把握と課題解決に不可欠な手法です。ExcelやGoogleスプレッドシート、Notionなどのツールを活用することで、効率的かつ精度の高い財務分析が可能です。
また、無料ツールを活用すれば専門知識がなくても手軽に分析を始められます。自社に合った方法を選び、経営戦略の質を向上させましょう。
マーケティング支援の専門家であるkoujitsuでは、戦略設計からサイト制作、広告運用までを一気通貫でサポートします。企業の特徴に合わせた最適なプランを提案し、成長を加速させるための取り組みを実行します。ぜひお気軽にご相談ください。






