
企業が成長を続けるためには、戦略的な組織運営が欠かせません。その中で組織戦略フレームワークは、経営の方向性を明確にし、組織の力を最大限に引き出す手法として活用されています。適切なフレームワークを導入することで、組織の課題 […]
企業が成長を続けるためには、戦略的な組織運営が欠かせません。その中で組織戦略フレームワークは、経営の方向性を明確にし、組織の力を最大限に引き出す手法として活用されています。適切なフレームワークを導入することで、組織の課題を把握し、最適な戦略を立てることが可能です。本記事では、組織戦略フレームワークの基本概念や種類を解説し、活用方法を紹介します。
組織戦略フレームワークの基本概念

組織戦略フレームワークは、企業が継続的に発展し、競争優位を確立するための分析・設計手法です。組織の目的や市場環境に応じて適切なフレームワークを選択することで、経営の方向性を明確にできます。
企業が成果を最大限に引き出すには、組織構造やリソース配分を適切に設計することが求められます。そのため、体系的な分析を通じて課題を可視化し、最適な戦略を立案することが必要です。これにより、市場の変化に対応しながら成長の機会を逃さず、柔軟な経営判断が可能になります。
多くの企業では「マッキンゼーの7S」「SWOT分析」「PPM」「PEST分析」「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」などのフレームワークを活用し、組織の最適化を図っています。これらを適切に使い分けることで、経営戦略がより実効性の高いものとなります。
組織戦略フレームワークを活用することで、企業は明確な指針を持ち、持続的な競争力を確保できます。適切なフレームワークを選び、組織の発展につなげることが大切です。
組織戦略とは
組織戦略は、事業戦略の実現に向けて、社員の力を最大限に引き出すための組織設計を指します。企業が継続的に発展するには、市場環境の変化に適応しながら、組織のあり方を見直し続ける必要があります。
企業の戦略が変われば、組織の理想像も変化するべきです。そのため、多くの企業がエンゲージメント向上や組織風土の改善に取り組み、社員の満足度を定期的に測定しています。社員のエンゲージメントが高い組織ほど、事業の推進力が強まるため、組織戦略の改善は経営の成否を左右します。
例えば、人的資本経営の観点から、企業は社員の価値観や働きがいを把握するために、サーベイやデータ分析を導入しています。これにより、組織の課題を明確にし、より良い環境づくりが可能です。
組織戦略は、単なる制度や仕組みではなく、企業の成長を支える根幹です。組織戦略を進化させ続けることで、環境の変化に対応し、競争力を維持できます。
事業戦略・人事戦略との違い
組織戦略は、事業戦略や人事戦略と連携しながらも、それぞれ異なる目的を持つ戦略です。事業戦略は「企業の目標を達成するための計画」、人事戦略は「人材の活用を通じて生産性を向上させる計画」です。一方、組織戦略は事業戦略の推進を支え、理想的な組織の形を実現するための指針として機能します。
企業が成長し続けるためには、事業戦略と連動した組織設計が欠かせません。適切な組織戦略がなければ、事業の方向性と人材活用が噛み合わず、組織全体のパフォーマンスが低下するリスクがあります。 そのため、企業は事業戦略と人事戦略をつなぐ役割として、組織戦略を策定し、状況に応じて最適な形へと進化させる必要があるでしょう。
例えば、多くの企業では、事業戦略に基づき、組織構造の再編や人材配置の見直しを行っています。具体的には、部門間の連携を強化し、スキル向上を促す仕組みを導入することで、事業戦略の実現を支援しています。
組織戦略は、単なる人事施策ではなく、企業全体の成長を支える大切な要素です。事業戦略や人事戦略と連携しながら、組織の最適化を進めることで、企業の競争力を維持し、持続的な発展を実現できます。
事業戦略についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
事業戦略とは?他の戦略との比較や手順・フレームワークを紹介
企業に組織戦略フレームワークが必要な理由
企業が成長を続けるためには、市場環境の変化に適応しながら、生産性を向上させる必要があります。そのためには、組織の課題を可視化し、最適な戦略を策定する「組織戦略フレームワーク」の活用が欠かせません。
市場は常に変化しており、従来の組織体制や考え方では競争優位性を維持することが難しくなっています。さらに、少子高齢化の影響により人材確保が厳しくなり、既存の社員のパフォーマンス向上が求められています。これらの課題に対応するためには、組織の生産性やエンゲージメントを高め、適材適所の配置を実現することが不可欠です。
例えば、企業は組織の現状を把握するために「コンピテンシー診断」や「はたらきがいサーベイ」を活用し、課題を明確にしています。これにより、業務の効率化や人材の定着率向上につながり、結果として企業の競争力が強化されます。
組織戦略フレームワークを導入することで、企業は市場の変化に対応しながら、組織のパフォーマンスを最大化できます。適切な戦略の策定と継続的な見直しを行うことで、持続的な成長が可能となります。
組織戦略フレームワークの4つの種類

組織戦略を効果的に策定・実行するには、適切なフレームワークを活用することが欠かせません。フレームワークを用いることで、組織の現状を的確に把握し、課題や強みを分析しながら、最適な戦略を導き出すことが可能です。
1.マッキンゼーの7S
マッキンゼーの7Sは、組織を構成する7つの要素をバランスよく調整し、最適化するためのフレームワークです。戦略の見直しや組織改革を進める際に活用され、組織全体の一貫性を確保しながら成長を促進します。
7Sの要素一覧
| 分類 | 要素 | 内容 |
| ハードの3S | 戦略(Strategy) | 目標を達成するための計画や方針 |
| 組織(Structure) | 組織の仕組みや構造 | |
| システム(System) | 業務フローや人事評価制度などの仕組み | |
| ソフトの4S | 経営スタイル(Style) | 経営層の思想や企業文化 |
| 人材(Staff) | 適切な人材の採用や配置 | |
| 組織のノウハウ(Skills) | 技術力やマーケティング力などの強み | |
| 価値観(Shared Value) | 組織の共通認識や企業の理念 |
ハードの3S(戦略・組織・システム)は比較的短期間で変更可能ですが、ソフトの4S(経営スタイル・人材・組織のノウハウ・価値観)は組織文化に関わるため、長期的な取り組みが必要です。
組織改革を行う際には、まず戦略や組織構造の見直しを進め、その後、企業文化や人材育成などのソフト面に取り組むことで、持続的な変革が実現できます。
マッキンゼーの7Sを活用することで、組織の課題を体系的に分析し、短期的な施策と長期的な取り組みのバランスを取りながら、組織のパフォーマンス向上を図ることが可能です。
2.SWOT分析
SWOT分析は、企業の内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を明確にするフレームワークです。組織の強みや機会を活かし、弱みや脅威に適切に対応することで、競争力のある組織戦略を構築できます。
| 分類 | 要素 | 内容 |
| 内部環境 | 強み(Strength) | 目標達成にプラスとなる自社の特性 |
| 弱み(Weakness) | 目標達成の障害となる自社の課題 | |
| 外部環境 | 機会(Opportunity) | 市場拡大の可能性や競争優位性 |
| 脅威(Threat) | 競争激化や市場縮小のリスク |
SWOT分析を活用することで、企業は市場環境を的確に把握し、持続的な成長を実現するための戦略を立案できます。また、内部要因と外部要因を掛け合わせた「クロスSWOT分析」を行うことで、より具体的な戦略策定が可能になるでしょう。
例えば、企業の強みを活かして市場の機会をつかむ(S×O)戦略や、弱みを克服しつつ外部の脅威に備える(W×T)戦略を導き出すことで、実践的な組織戦略の策定が可能です。
SWOT分析を通じて、組織の現状を多角的に分析し、適切な施策を実行することで、企業の競争力向上と成長を加速させることができます。
3.PPM
PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、市場成長率と市場占有率を基準に事業の成長性を評価し、資源の最適な配分を決定するフレームワークです。事業ごとのポジションを明確にすることで、経営資源を効果的に活用し、成長戦略を最適化できます。
| 分類 | 要素 | 内容 |
| 高成長・高シェア | 花形(Star) | 競争が激しいが、成長が期待できる事業 |
| 低成長・高シェア | 金のなる木(Cash Cow) | 安定した収益を生むが、大きな成長は見込めない事業 |
| 高成長・低シェア | 問題児(Problem Child) | 競争が激しく、将来性が不透明な事業 |
| 低成長・低シェア | 負け犬(Dog) | 収益が低く、投資対象から外すべき事業 |
PPMを活用することで、企業は成長性の高い分野に資源を集中させ、経営効率を高めることが可能です。特に、「花形」は継続的な投資によって「金のなる木」へと成長させることが求められます。一方、「負け犬」に分類される事業は、撤退や売却の選択肢を検討する必要があります。
例えば、多くの企業はPPMを活用し、市場成長率とシェアの変動を分析しながら、成長戦略の見直しを実施しています。これにより、リスクを抑えつつ、競争力のある分野に経営資源を集中させることが可能です。
PPMを適切に活用することで、企業は長期的な成長を視野に入れながら、戦略的な経営判断を行えます。
4.PEST分析
PEST分析は、企業の外部環境を「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点から整理し、組織戦略に活かすフレームワークです。企業が直接コントロールできない外部環境の変化を分析することで、リスクを最小限に抑えながら、成長の機会を見出すことができます。
| 分類 | 要素 | 内容 |
| 政治 | Politics | 法規制、税制、政府の政策、貿易ルール、国際関係の変化 |
| 経済 | Economy | 景気変動、金利、為替、雇用状況、インフレ・デフレ |
| 社会 | Society | 人口動態、ライフスタイル、消費者行動、価値観の変化 |
| 技術 | Technology | 技術革新、新技術の普及、デジタル化、AIの進展 |
PEST分析を活用することで、企業は市場環境の変化を予測し、競争力を維持できます。例えば、社会のデジタル化が加速する中で、新たなIT技術の導入が求められる場合、迅速に対応することで競争優位性を高めることができるでしょう。また、政府の規制強化が予想される場合、事前に影響を分析し、適切な対策を実行することも可能です。
企業が持続的に成長するためには、PEST分析を活用して市場環境の変化を適切に捉え、柔軟な戦略を策定することが求められます。
5.MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)
MVV(Mission・Vision・Value)は、企業の存在意義や目指す方向性、行動基準を明確にするフレームワークです。これを策定することで、社内外の共通認識が形成され、組織の一体感を強化することができます。
| 分類 | 要素 | 内容 |
| ミッション | Mission | 企業が社会に対して「なすべきこと」を示す理念 |
| ビジョン | Vision | 企業の「あるべき姿」や中長期的な目標 |
| バリュー | Value | 社員が共有し、実践すべき行動指針・価値観 |
MVVを明確にすることで、従業員一人ひとりが企業の方向性を理解し、組織全体の意思決定が統一されます。例えば、企業のミッションが「持続可能な社会の実現」であれば、ビジョンとして「環境に配慮した製品開発の推進」、バリューとして「環境負荷の低減を意識した行動」など、具体的な指針を定めることができます。
組織の成長を促進するためには、MVVを単なるスローガンにとどめず、日々の業務に取り入れ、企業文化として定着させることが求められます。
事業戦略で使えるフレームワークについてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
事業戦略で使えるフレームワーク活用方法9選!注意点も解説
組織戦略を考える上での4つのポイント
組織戦略を成功させるためには、戦略の策定だけでなく、その実行と継続的な改善が求められます。以下の4つのポイントを押さえることで、組織の方向性を明確にし、持続的な成長を実現できます。
1.組織全体の現状を把握する
組織戦略を策定する際には、まず現状を正確に把握することが不可欠です。組織の強みや課題を明確にすることで、適切な施策を導き出し、持続的な成長へとつなげることができます。
現状分析として、従業員のエンゲージメントを測定することが求められます。従業員が仕事に対してどの程度意欲を持ち、組織に貢献したいと考えているかを把握することで、モチベーション向上につながる施策の検討が可能です。次に、組織のビジョンや理念が従業員に浸透しているかを確認し、必要に応じて伝達方法を見直します。明確な方向性が共有されていない場合、組織内の連携が不十分になり、個々の行動が統一されにくくなるため、継続的な見直しが求められます。
さらに、業務プロセスの課題を洗い出し、非効率な部分やボトルネックを特定することも欠かせません。業務の流れを整理し、改善点を明確にすることで、生産性の向上につなげることができます。また、組織の拡大や市場環境の変化に適応できる体制が整っているかを検証し、必要に応じて組織構造を見直すことも不可欠です。
組織全体の現状を的確に把握することで、適切な戦略を策定し、持続的な成長を支えるための基盤を築くことができます。
2.企業において「ありたい姿」を明確にする
組織が成長し続けるためには、目指すべき「ありたい姿」を明確にすることが欠かせません。ビジョンや企業理念を明確にすることで、従業員の意識統一が図れ、組織全体の方向性を定めることができます。
まず、企業のミッション(存在意義)を明文化し、社会に対してどのような価値を提供するのかを明確にしなければなりません。そのうえで、中長期的な目標を設定することで、従業員が自身の役割を理解し、働く意義を実感できるようになります。さらに、企業文化や価値観を共有し、日々の行動指針として定めることで、従業員が迷うことなく意思決定を行い、統一した行動をとることが可能になります。
このように、企業の「ありたい姿」を明確にし、組織全体で共有することにより、戦略的な意思決定がスムーズに進み、組織の一体感を強化できるでしょう。
3.マネジメントの教育を行う
組織の成長を支えるためには、適切なマネジメント教育が欠かせません。リーダーシップや意思決定のスキルを磨くことで、組織全体の生産性が向上し、従業員のエンゲージメントも高まります。
まず、管理職が企業理念やビジョンを正しく理解し、部下に伝える力を養うことが求められるでしょう。さらに、チームの成果を最大化するためのコーチングやフィードバック手法を学ぶことで、的確な指導が可能になります。加えて、状況に応じた柔軟な対応力を鍛えることで、変化の激しい環境でも適切な判断を下せるようになります。
このように、マネジメント教育を徹底することで、組織全体のパフォーマンスが向上し、より強固なチームを築くことが可能です。
4.必要な人材の採用を進める
組織の成長には、適切な人材の確保が欠かせません。企業のビジョンや目標に沿った人材を採用することで、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。
まず、求める人材像を明確にし、スキルや経験だけでなく、企業文化や価値観に適合するかを判断することが求められます。その上で、適切な採用手法を選択し、ターゲットに応じた採用活動を実施することが肝心です。また、採用後の定着を促進するために、オンボーディングプロセスの整備も欠かせません。
このように、戦略的な採用活動を推進することで、組織の競争力を高め、長期的な成長を実現できます。
組織戦略に関するおすすめの本3選
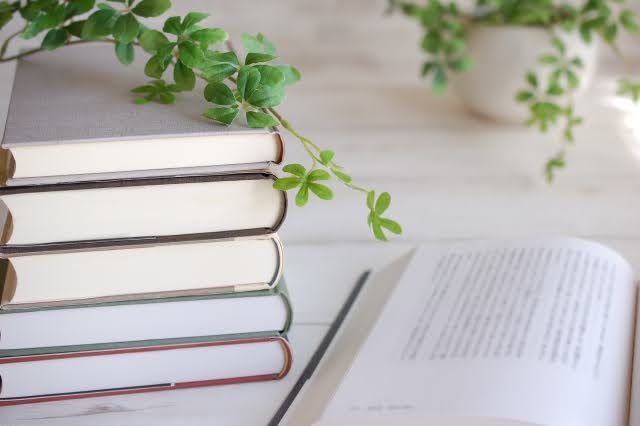
ここからは、組織戦略に役立つおすすめの本を3選紹介します。
1.『他者と働く―「わかりあえなさ」から始める組織論』
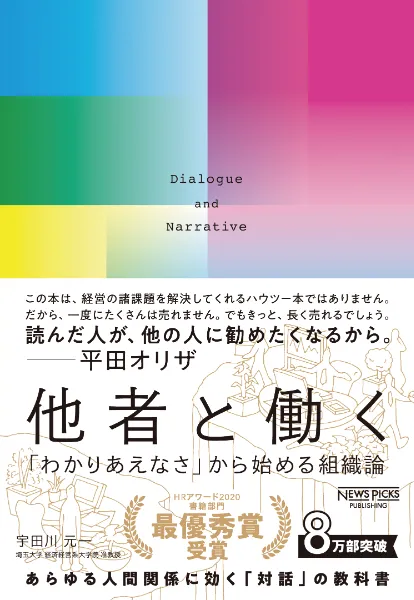
出典:他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論|本|宇田川元一(著)|NewsPicksパブリッシング |通販|Amazon
注目ポイント
- 相互理解を前提とせず、違いを活かすという視点を提案
- 立場や価値観の違いを乗り越え、新たな協力関係を築く方法を解説
- 問題解決の鍵は、個人の能力よりも関係性の質にあると示唆
料金
1,980円(税込み)
本の基本情報
| 出版社 | NewsPicksパブリッシング |
| 発売日 | 2019/10/4 |
| 著者 | 宇田川元一 |
※2025年3月時点
2.学習する組織――システム思考で未来を創造する
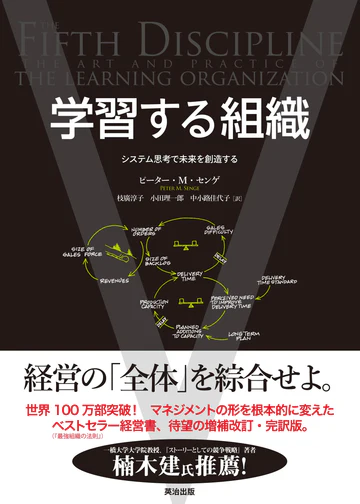
出典:学習する組織――システム思考で未来を創造する|本|ピーター M センゲ (著), 枝廣 淳子 (翻訳), 小田 理一郎 (翻訳), 中小路 佳代子 (翻訳)|英治出版|通販|Amazon
注目ポイント
- 全体の構造や因果関係を理解し、本質的な課題解決を目指す
- 個人と組織が共に成長する継続的な学びの文化を築く方法を提案
- 短期的でなく、組織が長期的に進化するための思考や文化の変革を促す
料金
3,850円(税込み)
本の基本情報
| 出版社 | 英治出版 |
| 発売日 | 2011/6/22 |
| 著者 | ピーター・M・センゲ(著), 枝廣淳子(訳), 小田理一郎(訳), 中小路佳代子(訳) |
※2025年3月時点
3.『組織は変われるか――経営トップから始まる「組織開発」』
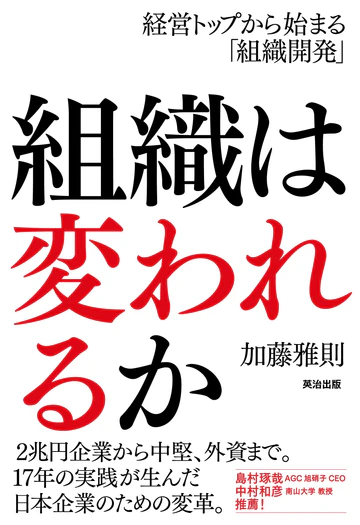
出典:組織は変われるか――経営トップから始まる「組織開発」|本|加藤雅則 (著)|英治出版|通販|Amazon
注目ポイント
- 技術的問題と適応課題を区別し、適切なアプローチ選択の重要性を解説
- 経営陣との対話を通じ、現場の変化を促すプロセスを紹介
- 組織課題について、経営陣たちが自らの責任と捉え、積極的に関与することが不可欠であるの協調
料金
1,643円(税込み)
本の基本情報
| 出版社 | 英治出版 |
| 発売日 | 2017/12/13 |
| 著者 | 加藤雅則 |
※2025年3月時点
まとめ
組織戦略フレームワークを活用することで、企業は課題を可視化し、成長を加速できます。組織戦略の要点は、現状把握、目標の明確化、マネジメント教育、人材採用の最適化です。
組織強化や目標管理でお悩みの方は、Koujitsuまでご相談ください。専門的なサポートを通じて、組織の生産性向上と成長を支援します。
マーケティング計画を立案する際に利用できるお役立ち資料をお求めの方はこちらからお申し込みください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





