
ポジショニングマップは、企業の戦略的な立ち位置を可視化するための強力なツールです。 自社と競合の差別化を図るためには、市場での立ち位置を明確に理解する必要があります。特に、適切な評価軸を選ぶことがポジショニングマップの効 […]
ポジショニングマップは、企業の戦略的な立ち位置を可視化するための強力なツールです。
自社と競合の差別化を図るためには、市場での立ち位置を明確に理解する必要があります。特に、適切な評価軸を選ぶことがポジショニングマップの効果を最大限に発揮するポイントです。
本記事では、ポジショニングマップの作成方法と活用方法を詳しく解説します。
ポジショニングマップとは
ポジショニングマップとは、顧客の視点から見た競合との位置関係を可視化するフレームワークのことです。縦軸と横軸に設定した2つの指標をもとに自社や競合の製品・サービスをプロットし、市場の立ち位置を把握します。これにより、独自性のあるポジションを見出し、差別化戦略を立てやすくなります。
この手法が重視される背景には、顧客ニーズの多様化と市場競争の激化があります。市場競争が激化する中、単純な優位性では差別化が困難です。ポジショニングマップは、自社の現在地と今後目指すべき方向を見極めるうえで効果的な判断材料となります。
価格と品質を軸に設定した場合、低価格・高品質なポジションに他社が少なければ、そこに参入する戦略が見えてきます。あるいは、サポート体制と導入実績を軸にすれば、信頼性を重視する顧客に対するアプローチのヒントを得ることが可能です。どの軸を選び、どう可視化するかによって、自社の打ち出すべき価値が明確になります。
このように、ポジショニングマップは競合分析や戦略立案の出発点となる大切な手法です。ビジネス環境が変化し続ける中で自社の存在意義を見直し、適切なポジションを確立することは、持続的な成長につながります。
ポジショニングマップを活用するメリット

ポジショニングマップを活用するとさまざまなメリットが得られます。ここでは、3つのメリットを解説します。
他社との差別化が図れる
ポジショニングマップを活用すれば市場での自社と競合の立ち位置を視覚的に整理できるため、どのように差別化を図るべきかが明らかになります。競合が密集しているエリアを避けて空白のポジションを見出すことで、独自の価値を打ち出す戦略の策定が可能です。
競争が激しい市場では、機能や価格などの単一の要素で勝負しても限界があります。ポジショニングマップによる差別化は、顧客に選ばれる理由を作るうえで欠かせない視点です。
BtoBサービスを提供する企業が「導入サポートの充実度」と「運用の柔軟性」を軸にしたマップを作成した場合、サポート体制の手厚さで勝負できる空白領域を見つけやすくなります。
このように、ポジショニングマップは他社との違いを明確に打ち出し、自社だけの価値を創出するための効果的な手段です。競合が多数存在する市場で選ばれるためには、可視化による戦略的な差別化が欠かせません。
顧客のニーズが明確になる
顧客が重視する価値基準を視覚的に捉えられる点も、ポジショニングマップを活用するメリットです。市場での各企業の立ち位置が整理されるため、どのようなニーズが求められているか、どこに満たされていないニーズが存在するかを把握しやすくなります。
製品やサービスがどのように評価されているのかを分析するには、顧客の選定基準をマトリクス上に落とし込むことが効果的です。特定の軸上で選ばれている企業群を確認すると、顧客が重視している要素が浮かび上がります。逆に、評価されていないエリアには、対応しきれていないニーズが潜んでいる可能性が考えられるでしょう。
このように、ポジショニングマップは市場全体の構造を可視化し、顧客のニーズを読み解くための効果的な分析ツールです。ニーズの的確な把握は、プロダクト開発やマーケティング戦略の質を高めるポイントとなります。
マーケティングの施策に役立つ
ポジショニングマップは、効果的なマーケティング施策を検討する際の判断材料として役立つ手段です。自社と競合の位置関係や市場構造を可視化することで、狙うべきターゲット層や訴求ポイントが明確になります。
あらかじめ市場全体の構図を把握したうえで施策を検討すれば、非効率な取り組みや競合との過度な競争は回避可能です。また、顧客が重視する評価軸が明確になれば、自社が訴求すべき強みや伝え方も最適化できます。
製品が「機能性」と「価格感」の中間に位置する場合、機能面の価値を強調しつつコストメリットを伝えるアプローチが役立つと判断できます。競合の打ち出し方との違いを踏まえたうえで、自社らしい伝え方を導き出せる点もメリットでしょう。
このように、ポジショニングマップはマーケティング活動の精度を高めるうえで効果的です。現状分析にとどまらず、戦略設計から実行段階まで一貫して活用できる点が大きな強みです。
新規事業のマーケティングについては、以下の記事もご覧ください。
ポジショニングマップの作り方
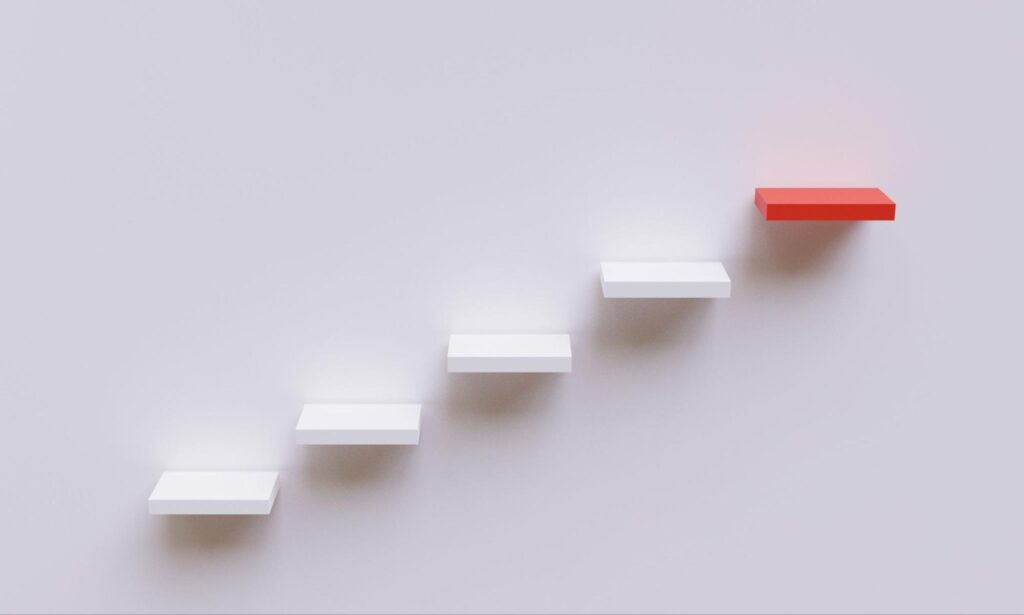
ポジショニングマップを作る際は、以下の4つのステップで進めるとスムーズです。ここでは、それぞれのステップを解説します。
KBF(購買決定要因)を整理する
ポジショニングマップを効果的に作成するためには、KBF(Key Buying Factors/購買決定要因)の明確化が欠かせません。顧客が商品やサービスを選ぶ際に重視している基準を把握することで、マップの軸設定が論理的かつ実用的になります。
KBFは業種や商材によって異なり、価格や品質だけでなく、使いやすさ、信頼性、サポート体制、導入スピードなど多様な観点が存在します。顧客の選定基準の洗い出しにより、競争の軸や差別化できるポイントの明確化が可能です。
こうした要因を抽出するには、既存顧客へのヒアリングやアンケート結果の分析、営業担当者の知見の収集などが役立ちます。複数の視点を交えて検討すると、より実態に即したKBFを把握できるでしょう。
KBFについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
KBFとは?KSFとの違いや具体例・決め方・活用のコツを解説!
マトリクスの軸を決める
ポジショニングマップを構築するうえで、マトリクスの軸設定は大切なステップです。軸の選定が適切であればあるほど自社や競合の位置づけが明確になり、効果的な分析結果につながります。
軸を決める際はKBF(購買決定要因)をもとに、顧客が重視している2つの要素を選びましょう。どちらも対照的で意味が重ならず、一方が高ければもう一方も必然的に高くなるような関係性を避けた軸の選定が基本です。
具体的には「価格」と「サポート体制」などのように直接的な関連性の少ない要素を掛け合わせると、それぞれの企業や製品がどのようなポジションにあるかを明確に可視化できます。
このように、軸の設定はポジショニングマップ全体の実効性を左右する要素です。顧客目線と自社の戦略を踏まえた軸選びを行い、より実践的で戦略的なマップを作成しましょう。
自社・他社の情報をマップに落とす
ポジショニングマップを作成する際は設定した軸に沿って自社と競合の情報を整理し、マトリクス上に配置します。この作業により、市場全体の構造が視覚化され、自社の立ち位置や差別化の余地を明確に捉えることが可能です。
自社と競合を正確に位置づけるには、客観的なデータや第三者の評価を基にした判断が不可欠です。企業ごとのサービス内容や価格帯、提供価値、ユーザーの評価などを基準に、相対的な位置を見極めましょう。主観に頼らず一定の評価基準に基づいたマップの作成によって、分析の信頼性が高まります。
整理する情報の正確さと分析の公平性が、マップの実効性を左右します。確かな判断につなげるためにも、事前の準備は慎重に行いましょう。
差別化できるポジションを検討する
ポジショニングマップを活用する最大の目的は、自社が市場の中で独自性を発揮できるポジションを見出すことです。競合が密集している領域ではなく、適切に空いているポジションを見極めると明確な差別化戦略を構築しやすくなります。
差別化可能な領域を探すには、自社の強みが活かせる軸上の位置に注目しなければなりません。マップ上で競合と重ならない場所に自社を置けるかどうかを確認し、なおかつ顧客のニーズと合致しているかを判断しましょう。ニーズが存在し、かつ競合が手薄な領域であれば、顧客に選ばれる確率が高まります。
また、既存の枠にとらわれず、新たな付加価値や提供手段を組み合わせると、独自の立ち位置が見えてくる可能性もあるでしょう。
このように、差別化できるポジションの検討は単なる分析にとどまらず、今後のブランド戦略や商品企画にも大きく影響する大切なプロセスです。
ポジショニングマップの軸の決め方
ポジショニングマップを作成する際は、適切な軸を決めることが大切です。ここでは、軸の決め方を3つ解説します。
ユーザー目線に基づいた項目
ポジショニングマップの軸は、ユーザーの視点を反映した項目を検討するとよいでしょう。実際の購買行動に直結する基準を軸に設定することで、顧客の価値判断を的確に捉えた分析が可能になります。
ユーザーが商品やサービスを選ぶ際は価格や品質だけでなく、サポート体制、利便性、導入までのスピードなど、さまざまな要素が影響します。企業側の都合で選定した軸ではなく、ユーザーが重視する基準を把握し、それに基づいた項目を設定するとより現実的な市場構造の可視化が可能です。
価格帯が同程度でも「操作のしやすさ」と「購入後の安心感」などの観点に違いがあれば、ユーザーの評価は大きく異なります。こうした違いを反映できる軸を設定できれば、自社が提供すべき価値や競合との違いも明確になり、訴求ポイントの整理にもつながります。
このように、ユーザー目線に立った軸の選定は、ポジショニングマップの実用性を高めるうえで欠かせない要素です。顧客が本当に求めている価値を見極めることが、効果的なポジショニングの第一歩となります。
自社の強みに基づいた項目
ポジショニングマップの軸を設定する際は、自社の強みを活かせる項目を意識しましょう。競合と比較して優位性を示せる要素を軸に含めれば差別化の方向性が明確になり、戦略展開にもつなげやすくなります。
強みの内容は企業によって異なりますが、独自の技術力、高い顧客満足度、対応スピード、柔軟なカスタマイズ性などは軸にしやすい要素です。他社より優れていると自負できる領域を抽出し、評価項目としてマップに反映させることで分析全体に一貫性が生まれます。
また、強みに合致する項目を軸に据えれば、自社の得意分野で競争優位を築きやすくなるでしょう。競合の得意分野に無理に合わせるのではなく、自社の特性を活かした立ち位置の選定にもつながります。
このように、競争力を発揮しやすい領域を見極める視点が、マップ活用の成否を左右します。
競合の強みに基づいた項目
競合の強みを意識した視点も、ポジショニングマップを構築するポイントです。競合がどの要素で評価されているかを分析すれば、自社が参入すべき領域や避けるべき土俵が明確になり、戦略に一貫性を持たせやすくなります。
競合の特徴を分析する際は、顧客からの評価や導入実績、ブランド力、技術的優位性、コスト競争力などに注目しましょう。業界内で定評のある要素を軸に設定することで、市場でのポジションの相対関係が見えやすくなります。また、競合が強みとしている項目をあえて軸に採用すると、自社との違いを際立たせるきっかけにもなります。
競争環境を正しく理解し、戦略の方向性を定めるうえでも効果的な手法です。
ポジショニングマップ作成の注意点
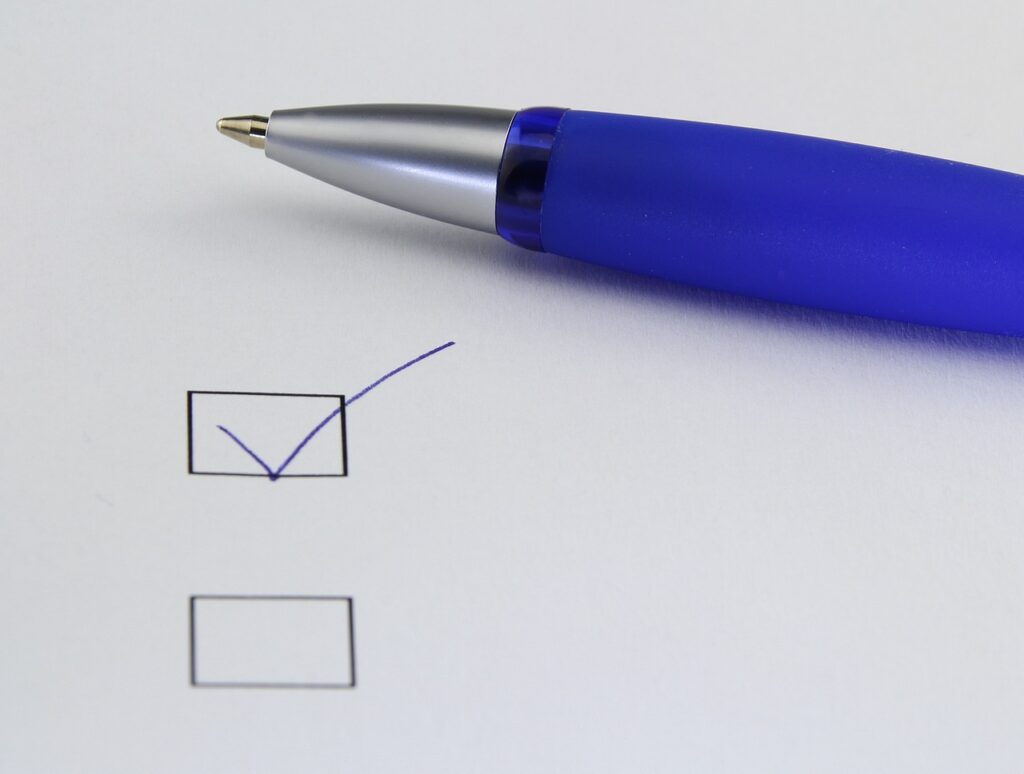
ポジショニングマップの効果を高めるには、注意点を押さえることが大切です。ここでは、3つの注意点を解説します。
軸同士の関連性が強い項目は避ける
ポジショニングマップを作成する際は、軸同士が独立しているかどうかに注目しましょう。関連性の強い項目を組み合わせると分析結果が偏りやすくなり、立ち位置の違いが明確に可視化できません。
「価格」と「コストパフォーマンス」のように自動的に両軸が高くなる関係性では分析の幅が狭まり、適切な差別化判断が難しくなります。軸には、それぞれが独立した評価基準として成立する項目を選ぶことが大切です。
異なる視点から構成された2軸であればユーザーの多様な選定基準を捉えやすくなり、競合との違いも明確に表現できます。情報の整理や戦略の立案にもつながるため、軸の設計段階から慎重に検討しましょう。
2軸で作ったほうが分析しやすい
ポジショニングマップは、軸を2つに限定すると視認性の高さと実用性を両立できます。3軸以上使って詳細な分析を行う方法も可能ですが、情報が複雑化するため注意が必要です。
分析のしやすさを重視するのであれば、2軸構成にしたほうが直感的に情報を把握しやすいでしょう。相対的な強みや弱み、市場の空白領域などを一目で確認でき、複雑な指標を組み込まなくても十分な洞察が得られます。
特に、初期段階で市場全体の構造を把握するには、2軸によるシンプルな可視化が最適です。戦略立案や他部門との共有時にも情報が伝わりやすく、分析の方向性をすばやく共有できます。
BtoCとBtoBは切り口を変える
ポジショニングマップは、BtoCとBtoBで軸の切り口を変えて作成することが大切です。対象となる顧客層の購買行動や重視する要素が異なるため、同じ視点で分析しても適切なポジションを把握できません。
BtoCでは、価格、デザイン、手軽さ、ブランドイメージなど感覚的な要素が重視されやすい一方、BtoBでは信頼性、サポート体制、導入コスト、運用効率など実務的な判断軸がポイントとなります。誰が意思決定に関与するか、何を重視して選ばれるかを踏まえて軸を設定することで、実態に即したマップの構築が可能です。
このように、ターゲットの特性を的確に捉える視点が、戦略の実効性を左右します。
まとめ
ポジショニングマップは市場での自社の立ち位置を明確にし、競合との差別化や戦略構築に役立つ手法です。KBFを踏まえて軸を設定し、ユーザー目線や自社・競合の強みを反映することで実態に即した分析が可能になります。目的に合った視点で活用し、今後のマーケティングや商品開発に役立てましょう。
マーケティング計画を立案する際に利用できるお役立ち資料をお求めの方はこちらからお申し込みください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





