
プロジェクトを円滑に進めるには、事前に管理の枠組みを整え、全体の進捗やリスクをしっかり把握することが重要です。どのような手法を選んでプロジェクトを動かしていくかは、プロジェクト規模やチーム体制、業界特性などによって大きく […]
プロジェクトを円滑に進めるには、事前に管理の枠組みを整え、全体の進捗やリスクをしっかり把握することが重要です。どのような手法を選んでプロジェクトを動かしていくかは、プロジェクト規模やチーム体制、業界特性などによって大きく変わります。
しかし、共通して求められるのは、誰が何をいつまでに行うのかを明確にする管理手法の導入と、コミュニケーションの徹底です。本記事では、プロジェクト管理の手法について、代表的な手法や選び方のポイント、成功のためのコツなどを詳しく解説します。
プロジェクト管理とは

プロジェクト管理とは、決められた期間や予算の制約の中で、設定した目標を達成するために進捗やリソース、リスクなどを計画的にコントロールすることです。チームメンバー間のコミュニケーションを促進し、期日や品質の目標を守りつつ成果物を完成へ導く行為を指します。
プロジェクト管理の必要性は、IT開発や建設事業など大規模なものだけでなく、小規模な新規サービスの立ち上げなどにも当てはまります。計画段階でタスクやリスクを洗い出し、実行中に状況を逐一把握することで、予測外の問題を最小限に抑えながらゴールに近づけるのが大きな特徴です。
プロジェクト管理の9つの手法
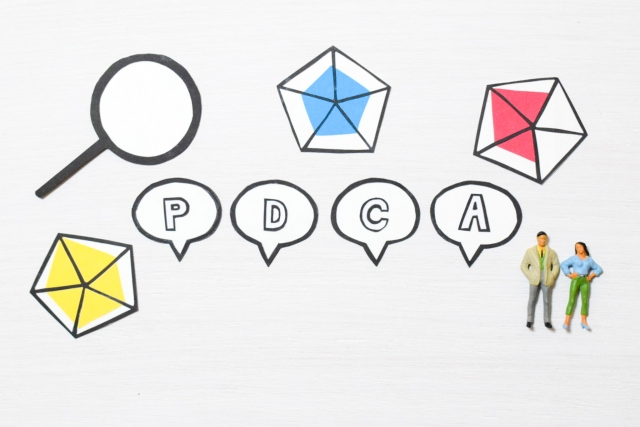
プロジェクト管理にはさまざまな手法が存在し、どの手法を選ぶかによって進め方やリスク管理の仕方が変わります。ここでは、代表的な9つの手法を紹介し、それぞれの特徴や活用シーンを簡潔にまとめます。
1.PMBOK(Project Management Body of Knowledge)
PMBOKは、アメリカのプロジェクトマネジメント協会(PMI)が体系化したプロジェクト管理の知識ガイドです。立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結といったライフサイクルに分け、タスクやコミュニケーション、リスクなどを包括的に管理する考え方を示します。
特に大規模プロジェクトや国際的な案件で活用されることが多く、世界的に認知されているプロジェクト管理の標準ともいえます。PMBOKをベースにした資格としてPMP(Project Management Professional)があり、プロジェクトマネージャーの専門性を証明する位置づけとなっています。
2.WBS(Work Breakdown Structure)
WBSは、プロジェクトを階層的に分解し、作業内容を整理するフレームワークです。大きな目標を小さいタスクの集合として可視化し、誰がいつ何を行うかを明確にできる利点があります。
たとえば、システム開発なら「要件定義→設計→実装→テスト」といった流れを更に細かくブレイクダウンして、作業漏れを防ぎながら進捗を管理します。WBSを使うことでチームメンバーが担当タスクを把握しやすくなり、工程間の依存関係を見極めるのにも役立ちます。
3.PERT(Program Evaluation and Review Technique)
PERTは、大規模プロジェクトのタスク順序や所要時間を図式化し、クリティカルパスを見つけてスケジュールを管理する手法です。各タスクをノード(円)で示し、矢印で依存関係を表現します。見落とされがちな依存関係を可視化することで、プロジェクト全体の最短完了時期が把握しやすくなります。
タスクの最短・最長所要時間を考慮するため、スケジュール遅延を早期に発見できるメリットがあります。特に工数が読みづらいプロジェクトでもPERT図を活用することで、クリティカルパス上のタスクに注力し、効率的な進行管理を可能にします。
4.CCPM(Critical Chain Project Management)
CCPMは、プロジェクトを進める中での「余剰時間の使い方」に注目し、バッファ管理を最適化する手法です。従来のクリティカルパスに「クリティカルチェーン」という考えを加え、メンバーそれぞれのリソース不足や多重タスクによる遅延リスクを抑えることを狙います。
具体的には、タスク間や最終段階にバッファを集約して配置し、メンバーが早めに着手・完了できるようにする仕組みを作ります。これにより、不必要に長い作業時間の確保を防ぎ、早期完了が可能になりやすいです。大規模プロジェクトで特に有効とされています。
5.PPM(Project Portfolio Management)
PPMは、企業が複数のプロジェクトを同時並行で進行する場合に、全体の投資や成果を最適化する観点からプロジェクト群を管理する方法です。単体のプロジェクトごとに最大利益を追求するのではなく、企業全体のリソース配分やリスク分散を考慮して評価・調整を行います。
たとえば、新規開発案件とコスト削減案件が競合する場合、どちらを優先するかを収益性や戦略的重要度から判断するのがPPMの特徴です。複数のプロジェクトをトータルで見渡し、長期的な視点で企業価値を高めるのが狙いです。
6.P2M(Project & Program Management)
P2Mは、日本で開発されたプロジェクトマネジメントのフレームワークで、単なるプロジェクトの進行管理だけでなく、プログラム(複数のプロジェクトの集合体)やイノベーションの創出まで考慮しています。公共事業や大規模インフラ開発など、社会的インパクトが大きい分野での活用が期待されています。
PMBOKと似ていますが、日本の事業環境や組織文化に合わせて定義されている点が特徴です。戦略的な事業ポートフォリオの構築から、個々のプロジェクトの管理手法までを包含しており、総合的なマネジメント能力を求める企業で導入される例があります。
7.ガントチャート
ガントチャートは、縦軸にタスク、横軸に時間を取り、各タスクの開始日や終了日を棒状で表すスケジュール管理の手法です。プロジェクトメンバー全員が一目で進捗や残り期間を確認できるので、進行管理の基本ツールとして幅広く導入されています。
特に、WBSと組み合わせるとタスクが分かりやすく整理され、担当者や依存関係が明確化しやすいです。Excelやプロジェクト管理ツールを使って容易に作成できるため、小規模から大規模まで幅広いプロジェクトで活用される実績があります。
8.かんばん方式(カンバン)
かんばん方式は、トヨタ生産方式で知られるように、必要なものを必要なタイミングで供給する「ジャストインタイム」を実現する仕組みです。ソフトウェア開発ではタスクを「To Do」「Doing」「Done」などのボードに可視化し、作業の流れやボトルネックを把握しやすくする手法として利用されています。
進捗をカードや付箋などで管理し、チームメンバーが現在の状況をリアルタイムで把握できる点がメリットです。タスクの停滞や負荷偏りがあれば即座に調整が可能であり、アジャイル開発や小規模チームで特に有効とされています。
9.ウォーターフォールとアジャイル
ウォーターフォールは、要件定義→設計→実装→テスト→運用といった工程を順番に進める伝統的な開発手法です。工程が明確で管理しやすい反面、後工程での仕様変更が困難になるデメリットがあります。
一方、アジャイルは小さな単位で反復的に開発を進め、顧客やチームのフィードバックを速やかに反映するスタイルをとります。仕様変更に柔軟に対応できる利点がある反面、管理の難易度が上がることもあります。プロジェクトの特性や期間、メンバー構成に応じてどちらの手法が適しているかを検討することが大切です。
プロジェクト管理手法の選び方

プロジェクトの内容や企業の文化、チーム規模によって適した管理手法は異なります。ここでは「目的から選ぶ」「組織規模に合わせる」「プロジェクト難易度を考慮する」という3つの選び方のポイントを解説します。
プロジェクト管理の目的から選ぶ
まずはプロジェクトが目指すゴールや特徴に応じて手法を選ぶことが重要です。品質保証を最優先するならPMBOKなど体系的に管理する手法が向いています。一方、スピード重視で途中の仕様変更に柔軟に対応したい場合はアジャイル開発が適しています。
要件が固まっており変更リスクが低いプロジェクトなら、ウォーターフォールで無駄なく進行しやすいです。逆に、顧客のフィードバックを繰り返し取り入れる必要があるのなら、反復的に開発するスプリント方式を考えても良いでしょう。自社の目的やプロジェクトの性質に応じて、最適な手法を見極めてください。
組織規模に合わせた手法を選ぶ
小規模プロジェクトで大企業向けの複雑なフレームワークを適用すると、手続きやドキュメントが過剰になり、かえって生産性が落ちるケースがあります。逆に大規模プロジェクトなのに簡易的な手法だけで管理しようとすると、進捗やリソースの把握が追いつかず混乱が発生しやすいです。
チーム人数やプロジェクトの規模感に合わせて、どのくらいのプロセスを設定するかを調整すると良いです。たとえば、数人のチームならかんばん方式で十分な場合もありますが、数百人規模の開発ではPMBOKを基盤とした厳格なプロセスが必要になるかもしれません。
プロジェクトの難易度を考慮して手法を選ぶ
技術的に難しいプロジェクトや変化が激しい場合は、小さなゴールを設定して短いサイクルで開発・テストを繰り返すアジャイル的なアプローチが向いています。一方、要件が比較的安定している案件や公共事業などは、ウォーターフォールモデルを採用したほうが管理がスムーズです。
複数の手法を部分的に組み合わせる方法もあります。例えば、基本設計まではウォーターフォール、機能追加フェーズはアジャイルといったハイブリッド運用を行う企業も増えています。プロジェクトの難易度やリスク要因を事前に分析し、柔軟に選択することが成功の鍵です。
プロジェクトを成功させる6つのポイント
プロジェクトを完遂するには手法だけでなく、運用面やコミュニケーションなども含めた総合的なマネジメントが必要です。ここでは、リソース確保やトラブル対策など、成功に欠かせない6つのポイントを紹介します。
1.プロジェクトのリソースを十分確保する
プロジェクトを円滑に進めるには、適切な人材や予算、時間が不可欠です。担当者の能力が不足していたり、人数が足りなかったりすると、タスクが滞ってスケジュールが崩れる可能性があります。特に開発やマーケティングなど専門スキルが求められる分野ではリソース確保が優先事項となります。
また、予算面でも想定外のコストが発生することを見越し、ある程度のバッファを設けておくとリスク対応がしやすいです。事前の段階で企業内の合意を取り付け、必要な資源を手厚く準備しておくことで、後々の修正対応を最小限に抑えられます。
2.綿密なコミュニケーションを意識する
プロジェクトが失敗に陥る大きな要因のひとつに、チーム内外とのコミュニケーション不足があります。進捗報告や問題発覚時の連絡が遅れると、スケジュールの遅延や品質低下に直結するリスクが高まります。
定期ミーティングやチャットツールなどを活用し、情報共有をリアルタイムで行う仕組みを整備することが重要です。タスクの担当者とステークホルダーをはっきりさせ、承認のフローを明確にしておけば、誰がいつ何を決めるのかが一目瞭然となります。このように、些細な問題でもすぐに共有できる環境を作ることがプロジェクト成功の鍵です。
3.工程を細分化して管理する
大きなタスクを一度に管理しようとすると、どこでどんな問題が起きているかを把握しづらくなります。WBS(Work Breakdown Structure)を使って工程を細分化し、それぞれに対して担当者や完了条件を設定すると、遅延や漏れが減りやすいです。
具体的には、開発工程なら「要件定義」「設計」「実装」「テスト」などに分解し、さらにステップごとにサブタスクを設ける方法が考えられます。こうして細分化されたタスクには工数や時間を明示しておき、ガントチャートなどを用いて視覚的に進捗を管理すると全体像をつかみやすくなります。
4.情報共有を徹底する
プロジェクトの進行に関わる情報が一部のメンバーだけに留まっていると、代替要員が不足したり、同じ質問やトラブル対応を繰り返したりする無駄が生じます。クラウドストレージやプロジェクト管理ツールを使って、関連ドキュメントや進捗データを誰でもアクセスできるようにすることが理想的です。
週次や月次で行われる進捗報告だけでなく、タスクの完了や問題発生などイベント単位でアップデートを行う仕組みを作りましょう。既存の情報を検索しやすい状態にしておくと、メンバーが異動や欠員になってもスムーズに対応しやすくなります。
5.トラブル発生時の対策を事前に検討する
どんなに慎重に計画を立てても、想定外のトラブルや仕様変更が起きる可能性は避けられません。そのため、リスクマネジメントの観点から事前に「起こり得る最悪のシナリオ」と「対処方法」をリストアップしておくことが大切です。
たとえば、主要メンバーの離職や外注先の納期遅延、予算超過などを想定し、緊急時にどのような意思決定を行うか明文化しておきます。リスクをゼロにするのは困難ですが、起きた際の対応速度と連携が早ければ、プロジェクト全体への影響を軽減できます。
6.プロジェクト管理ツールを活用する
プロジェクト管理ツールは、タスクの登録や割り当て、進捗表示などをワンストップで行えるシステムです。ガントチャートやかんばん方式など、複数の管理手法がサポートされているツールも多く、プロジェクトの可視化に大きく貢献します。
ツール上でコミュニケーションを行えば、メールのやり取りを最小限に抑え、誰がどの作業をしているかをリアルタイムで共有できます。クラウド型であればリモートワークにも対応しやすく、メンバー同士の連携が強化される利点があります。導入時にはチーム全員に使い方を周知し、運用ルールを定めると円滑に活用できます。
プロジェクト管理の注意点
プロジェクト管理を導入しても、手法の選び方や運用方法を誤れば、逆にチームが疲弊したり書類作成に追われる状況になりかねません。特に、タスク管理とコミュニケーションが分離していたり、トップダウンばかりの意思決定が続くと、現場の柔軟性が失われる恐れがあります。
さらに、メンバーのモチベーション維持も考慮しなければなりません。定期的にタスクの負荷を見直し、必要があれば再割り当てや外注の検討を行うと良いです。プロジェクト全体の方向性と進捗を把握しながら、必要最小限の管理で最大の成果を目指すバランスを取り続けることが大切です。
まとめ
プロジェクト管理の手法は多岐にわたり、それぞれが異なる特徴や得意分野を持っています。PMBOKやWBS、アジャイルなどの手法を単独で使う場合もあれば、プロジェクトの規模や目的に応じて組み合わせる場合もあります。大切なのは、チームとプロジェクトの特性を見極め、最適な方法を選んで実践することです。
さらに、コミュニケーションやリスク管理、リソース確保など、運用面のポイントを押さえておけば、スケジュール遅延や品質低下を未然に防ぐことができます。プロジェクト管理を堅固に行うことで、組織全体の生産性が向上し、プロジェクトの成功確率を大きく高められます。目的と手法を適切に結びつけながら、失敗を恐れずに実践してみてください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





