
企業で従業員の成長を促し、組織の生産性を向上させるためには、人事評価制度が欠かせません。適切な評価制度を導入することで、従業員のモチベーション向上や公正な処遇の実現が可能になります。しかし、評価基準が不明確だったり、制度 […]
企業で従業員の成長を促し、組織の生産性を向上させるためには、人事評価制度が欠かせません。適切な評価制度を導入することで、従業員のモチベーション向上や公正な処遇の実現が可能になります。しかし、評価基準が不明確だったり、制度の機能が失われていたりすると、逆に不満を生む原因にもなります。
本記事では、人事評価制度の基本から、導入のメリット・デメリット、評価手法、具体的な作成手順まで詳しく解説します。自社に最適な評価制度を設計し、企業の成長と従業員の満足度向上につなげるためのポイントを学んでいきましょう。
人事評価制度とは
人事評価制度とは、従業員の業績や能力、行動を評価し、それに基づいて昇進・昇給・配置転換などの人事決定を行う仕組みです。適切な制度設計と運用により、公平な評価を実現し、企業の成長と従業員のモチベーション向上を促すことができます。企業の競争力強化にも直結するため、多くの組織で導入が進められています。
人事評価制度が重要視される背景
近年、人事評価制度の重要性がますます高まっています。その背景には、労働市場の変化や働き方の多様化、企業の競争環境の激化などがあります。終身雇用制度の崩壊や成果主義の普及により、従来の年功序列型の評価では従業員のモチベーション維持が難しくなっています。
また、テレワークの普及により、従業員の働きぶりを直接観察することが難しくなったため、客観的な評価基準の整備が求められています。公正な評価制度がなければ、従業員の不満が蓄積し、離職率の上昇につながるリスクも高まります。さらに、適切な人事評価は、企業の成長戦略や人材育成の方針とも密接に関係しており、従業員のキャリア形成を支援する役割も担っています。
このような背景から、多くの企業が従来の評価制度を見直し、新たな仕組みの導入を進めています。評価の透明性や納得感を高めるために、データやAIを活用した評価制度の導入も検討されており、今後ますます注目度が増していくと考えられます。
人事評価をする際や、ビジネスの現場で役立つ思考法について以下の記事でまとめておりますので、ぜひご覧ください。
ラテラルシンキングとは?発想力と問題解決力を高める方法を解説
人事評価制度を導入するメリット・デメリット
人事評価制度の導入には、多くのメリットがありますが、適切に運用しなければデメリットも発生します。以下の表で、それぞれのポイントを整理します。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 公平性の向上 | 評価基準が明確になり、従業員が納得しやすい | 評価者の主観が入ると、公平性が損なわれる可能性がある |
| モチベーションの向上 | 昇給・昇進が明確になり、従業員が意欲的に働ける | 過度な競争が発生し、チームワークが損なわれる恐れがある |
| 人材育成の促進 | 強みや課題を明確にし、適切な研修や教育を実施できる | 評価基準が不明確だと、従業員が何を目指せば良いのか分からなくなる |
| 組織の成長支援 | 企業の目標と従業員の成長を結び付けられる | 制度の設計が難しく、適切に運用しないと逆効果になる可能性がある |
| 業績向上 | 成果を評価することで、従業員のパフォーマンスが上がる | 短期的な成果を重視しすぎると、長期的な成長につながらない可能性がある |
このように、人事評価制度にはさまざまなメリットとデメリットがあります。企業が導入を検討する際には、自社の文化や経営方針に合った制度設計を行い、適切に運用することが大切です。
人事評価制度を策定するための5ステップ

効果的な人事評価制度を導入するためには、適切なプロセスを踏むことが不可欠です。ここでは、制度を策定し、スムーズに運用するための5つのステップを紹介します。
STEP1. 現状の課題を把握して制度の目的を明確にする
人事評価制度を導入する前に、まずは現状の課題を把握し、制度の目的を明確にすることが大切です。評価基準が不明確で従業員のモチベーションが低下している、評価結果が昇給や昇進に適切に反映されていないなど、課題を洗い出す必要があります。
そのために、従業員や管理職へのヒアリングやアンケート調査、過去の評価データの分析を行い、具体的な問題点を把握します。また、他社の評価制度を参考にすることで、自社に適した基準を検討することも可能です。目的を明確にすることで、従業員が納得しやすく、企業の成長にも貢献できる評価制度を構築できます。
STEP2. 評価基準と評価項目を策定する
評価基準と評価項目の策定では、「何を評価するのか」「どのように評価するのか」を明確にすることが求められます。基準を設定することで、従業員は自分が何を達成すべきかを理解しやすくなり、評価の透明性も向上します。一般的に「業績評価」「能力評価」「行動評価」などが基準となります。
例えば、営業職では売上目標の達成率を業績評価として設定し、リーダーシップやチームワークを能力評価に含めることが可能です。また、企業理念を反映した項目を組み込むことで、組織文化に適した評価制度を作ることができます。
STEP3. 運用ルールとフィードバック方法を決める
評価制度を効果的に機能させるためには、運用ルールを明確に定める必要があります。具体的には、評価の頻度や評価者の選定、評価結果の活用方法などを決めておくことが大切です。
例えば、評価を年1回にするのか、四半期ごとに実施するのかによって、運用の手間や従業員の意識も変わってきます。また、評価者が直属の上司だけなのか、複数の関係者を含めるのかによって、公平性にも影響を与えます。
従業員へのフィードバック方法も欠かせないポイントです。評価結果を一方的に通知するだけではなく、フィードバック面談を設けて、従業員が納得できる形で説明することが求められます。フィードバックを通じて、従業員の成長課題や今後のキャリアパスを明確にすることで、評価制度を単なる査定ではなく、成長を促す仕組みとして機能させることができます。
STEP4. 社内へ周知して導入・試験運用を行う
評価制度を策定した後は、社内へ周知し、試験運用を行うことが大切です。新しい評価制度は、従業員にとって大きな変化となるため、事前にしっかりと説明し、理解を促すことが必要です。説明会や研修を実施し、評価の目的や評価基準、運用ルールを伝えることで、従業員の不安を軽減し、スムーズな導入が可能になります。
また、いきなり本格運用するのではなく、試験運用を行うことで、制度の問題点を洗い出すことができます。例えば、一部の部署やチームで試験的に評価を実施し、フィードバックを収集することで、実際の運用面での課題を把握し、必要な調整を行えます。
試験運用の結果をもとに、評価基準の修正や運用ルールの見直しを行い、制度をより効果的なものへとブラッシュアップすることが大切です。
STEP5. 制度の改善・最適化を行い継続的に運用する
人事評価制度は、一度導入すれば終わりではなく、継続的に改善・最適化を行うことが大切です。制度を運用する中で、評価基準が曖昧で従業員の納得感が得られない、評価の負担が大きすぎるなどの問題が生じることがあります。
こうした課題を放置すると、制度が形骸化し、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。そのため、定期的に評価制度を見直し、必要に応じて修正を加えていくことが求められます。
具体的な改善方法としては、従業員や管理職へのアンケート調査やヒアリングを実施し、制度に関する意見を収集することが効果的です。また、評価結果と業績の相関を分析し、評価基準が適切かどうかを検証することも欠かせません。
加えて、外部の人事制度コンサルタントの意見を取り入れることで、より客観的な視点から制度を改善することも可能です。こうした継続的な見直しを行うことで、企業の成長や組織の変化に対応した最適な人事評価制度を維持できます。
人事評価制度での主な評価の手法5選

人事評価制度にはさまざまな手法があり、企業の目的や文化に応じて適切なものを選択することが大切です。ここでは、代表的な5つの評価手法を紹介します。
1. 目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO: Management by Objectives)は、従業員が自身の目標を設定し、その達成度に基づいて評価を行う手法です。一般的には、期初に上司と部下が話し合いながら目標を設定し、期末に達成状況を確認する形で運用されます。
この手法のメリットは、従業員が主体的に目標を決めることで、モチベーションが向上しやすい点です。また、具体的な目標があることで、業務の優先順位を明確にしやすくなります。
一方で、目標が適切でない場合、現実的に達成困難だったり、逆に簡単すぎて成長につながらなかったりするリスクもあります。そのため、上司が適切なフィードバックを行い、目標設定の質を高めることが大切です。
2. コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、業務で成果を上げるために必要な能力や行動特性を基準として、従業員のパフォーマンスを評価する手法です。例えば、リーダーシップ、問題解決力、チームワークなど、職種ごとに求められるスキルを定義し、それに基づいて評価を行います。
この手法のメリットは、単なる業績評価にとどまらず、従業員の成長につながる行動を促進できる点です。また、職種ごとの成功要因を明確にすることで、採用や育成にも活用できます。一方で、評価項目が抽象的になりやすく、評価者の主観が入りやすい課題もあります。そのため、具体的な評価基準や行動例を設定し、評価のばらつきを抑えることが大切です。
3. 360度評価
360度評価は、上司だけでなく同僚や部下、他部署の関係者など、複数の視点から従業員を評価する手法です。評価の客観性を高めることができ、特にリーダーシップやコミュニケーション能力の評価に適しています。
この手法のメリットは、さまざまな立場の人からのフィードバックを得られる点にあります。上司だけでは分からない日常の働きぶりを把握しやすく、従業員の自己認識を深める機会にもなります。
一方で、評価者の関係性や主観に影響を受けやすいデメリットがあります。公平な評価を行うためには、評価基準を明確にし、匿名性を確保するなどの工夫が必要です。
4. 能力評価
能力評価は、従業員のスキルや専門知識、問題解決力などを基準に評価を行う手法です。特に専門職や技術職で効果的であり、従業員のスキルアップや適材適所の人材配置に役立ちます。
この手法のメリットは、客観的なスキル評価が可能になり、人材育成の方向性を明確にできる点です。一方で、評価基準が曖昧だと主観的になりやすく、評価者によって結果がばらつくリスクもあります。そのため、具体的な指標を設け、測定可能な形で評価を行うことが大切です。
5. 年功評価
年功評価とは、従業員の勤続年数や経験に応じて評価を行う手法です。特に、日本の伝統的な企業文化に根付いており、長年の貢献を重視する傾向があります。一定の年数を経過すると昇給や昇進が行われるため、安定したキャリアパスを提供しやすいのが特徴です。
この手法のメリットは、長期的な雇用の安定を図れる点にあります。従業員が安心して働ける環境が整い、組織の一体感が生まれやすくなります。また、経験を積んだ従業員が組織の中心となることで、社内のノウハウが蓄積されやすい利点もあります。
一方で、勤続年数が長いだけで評価されるため、成果を重視する企業文化とは相性が悪い場合があります。若手のモチベーション低下や、能力の高い人材の流出につながる可能性もあるため、能力評価や業績評価と組み合わせて活用するのが理想的です。
評価される際に優位に立てるスキルを身に着けたい方はこちらの記事をご覧ください。
事業戦略スキルとは?必要な能力や立て方・フレームワークを解説!
人事評価制度の6つの手順の作り方

人事評価制度を効果的に機能させるためには、適切な手順に沿って設計・導入することが大切です。ここでは、人事評価制度を作る際の6つの基本的な手順を解説します。
1. 社内全体の現状を把握する
まず、現在の人事評価制度がどのように運用されているのか、またどのような課題があるのかを把握することが欠かせません。評価基準が不明確で従業員の納得感が得られていない、評価が形骸化している、評価結果が昇給や昇進に適切に反映されていないなどの問題がないかを確認します。
従業員や管理職へのヒアリング、アンケート調査、過去の評価データの分析を行い、制度改善のための方向性を定めましょう。
2. 評価制度を導入する目的を設定する
次に、評価制度を導入する目的を明確にする必要があります。例えば、「従業員のモチベーション向上」「成果に応じた公平な処遇」「人材育成の促進」など、企業のビジョンや経営戦略に沿った目的を設定しましょう。
目的が曖昧だと、評価基準や運用方針がブレてしまい、従業員の納得感を得ることが難しくなります。目的を明確にすることで、評価制度が企業の成長に貢献する仕組みとして機能しやすくなります。
3. 評価制度と評価基準を決める
評価制度の目的が明確になったら、次に評価基準を決定します。評価基準には、業績評価(売上や成果)、能力評価(スキルや知識)、行動評価(チームワークやリーダーシップ)などがあります。
企業の方針や職種に応じて、適切な評価基準を設定することが大切です。評価基準が不明確だと、評価者によって判断がバラバラになり、公平性が損なわれる可能性があります。そのため、できるだけ具体的な基準を設定し、従業員が納得できる制度を作ることが求められます。
4. 評価項目を作成する
評価基準を決めたら、それに基づく具体的な評価項目を作成します。例えば、営業職の場合、「売上目標の達成率」「新規顧客の獲得数」「顧客満足度」などを評価項目として設定することが考えられます。
また、管理職であれば、「部下の育成状況」「組織のマネジメント力」などの要素を評価に組み込むことができます。評価項目を明確にすることで、従業員が何を意識して業務に取り組めばよいのかを理解しやすくなり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
5. 評価方法やルールを一律に定める
評価基準や項目が決まったら、それをどのように評価するのか、具体的なルールを定める必要があります。例えば、評価を年に何回実施するのか、誰が評価を行うのか、どのようなスコアリング方法を採用するのかなどを決めておきます。
また、評価結果のフィードバック方法も明確にし、従業員が評価を受けた後にどのようなアクションを取るべきかを分かりやすく示すことが大切です。評価ルールが不明確だと、制度が形骸化し、従業員の不信感を招く原因になるため、事前にしっかりと整備しておくことが求められるでしょう。
6. 社内へ浸透させて運用を始める
最後に、策定した評価制度を社内に浸透させ、運用を開始します。従業員が制度を理解し、納得して活用できるようにするためには、説明会や研修を実施することが効果的です。また、運用開始後も、評価制度が適切に機能しているかを定期的に確認し、必要に応じて改善を行うことが大切です。
特に、初めて導入する場合は試験運用を行い、従業員からのフィードバックを収集することで、実際の運用面での課題を把握しやすくなります。継続的な改善を行いながら、組織に適した評価制度を確立していきましょう。
人事評価の作り方に関するおすすめの本3選
ここからは、人事評価の作り方に関する書籍を3つ厳選してご紹介します。
1.人事評価はもういらない 成果主義人事の限界
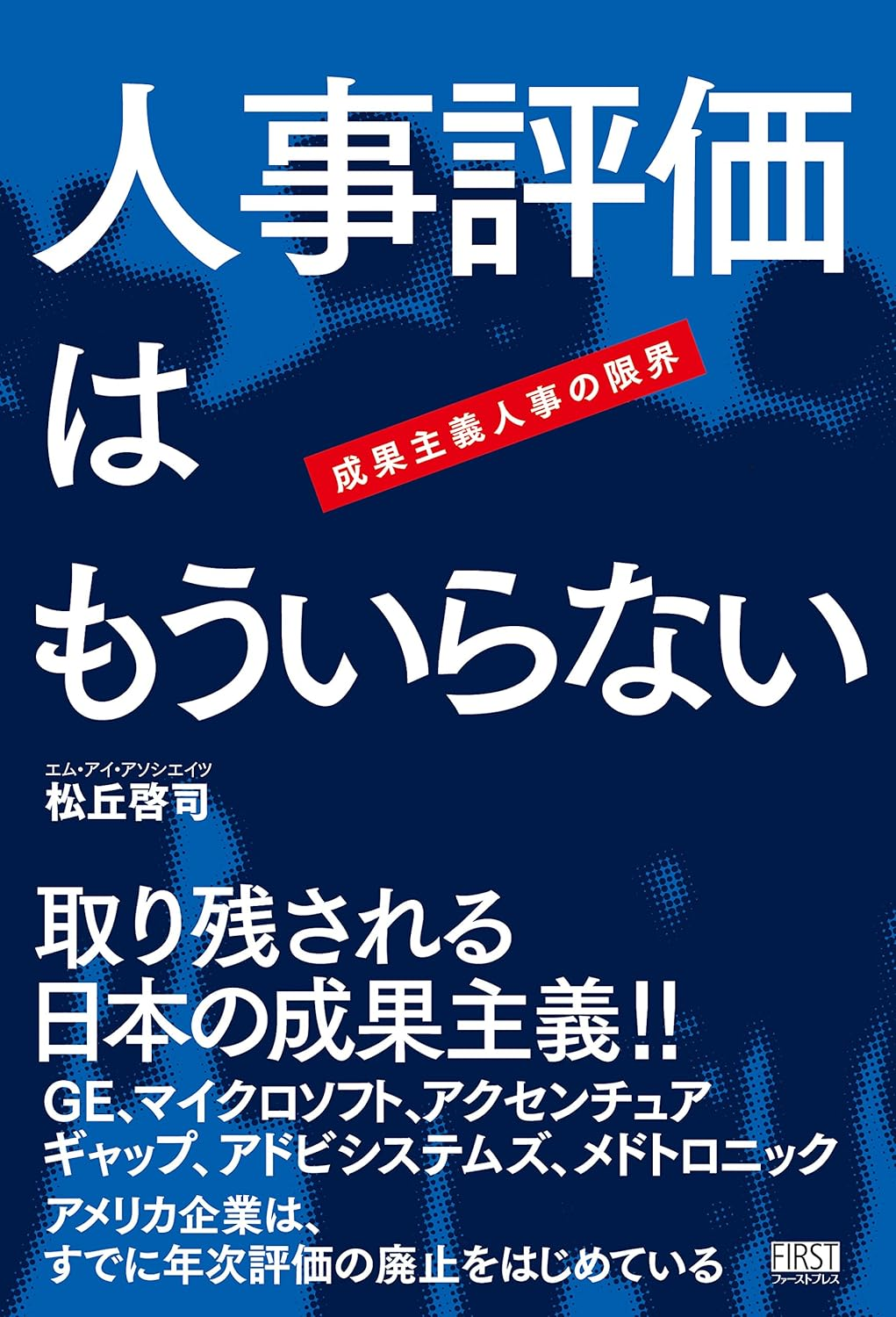
出典:人事評価はもういらない 成果主義人事の限界|本|松丘 啓司 (著)|ファーストプレス|通販|Amazon
注目ポイント
- 年次評価の限界と廃止の動きを紹介
- 多様な専門性や価値観を持った人材を、画一的な尺度で評価する難しさを指摘
- 定期的な評価でなく、日常的なフィードバックを通じて、社員のパフォーマンス向上と組織の柔軟性を高めるアプローチを提案
料金
1,237円(税込み)
本の基本情報
| 出版社 | ファーストプレス |
| 発売日 | 2016/10/15 |
| 著者 | 松丘 啓司 |
※2025年3月時点
2.人事評価制度が50分で理解でき、1日で完成する本 (忙しい社長のためのビジネス絵本)
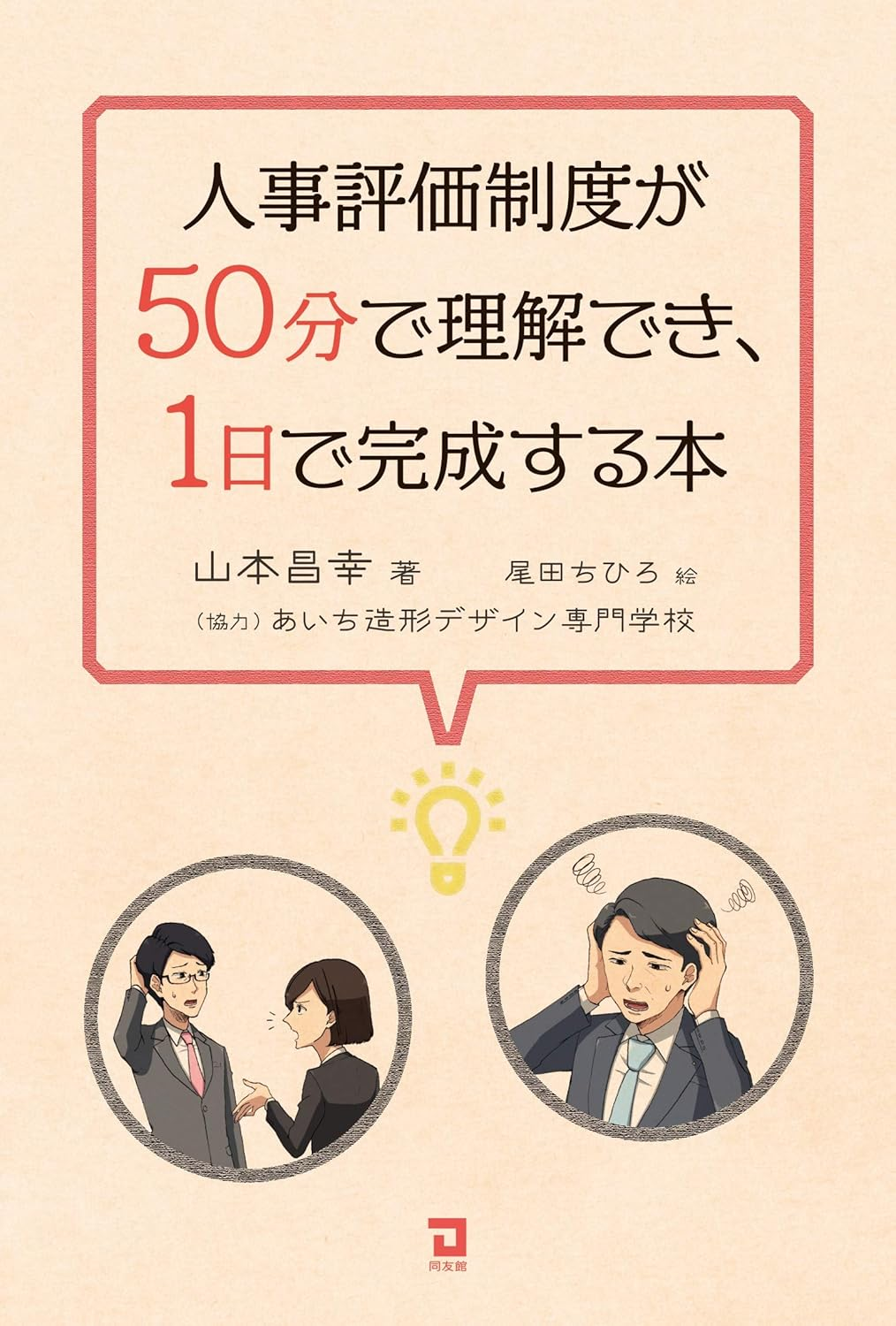
出典:人事評価制度が50分で理解でき、1日で完成する本 (忙しい社長のためのビジネス絵本)|本|山本昌幸 (著)|同友館|通販|Amazon
注目ポイント
- 50分で理解し、1日で自社に適用できる実践的な内容が特徴
- 人事評価制度に馴染みのない人にも理解しやすいよう、絵本形式で基本概念から導入手順まで丁寧に説明
- 人材育成と組織繁栄を達成するための戦略を紹介
料金
1,650円(税込み)
本の基本情報
| 出版社 | 同友館 |
| 発売日 | 2020/1/28 |
| 著者 | 山本昌幸 |
※2025年3月時点
3.改訂新版 小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方【テンプレート・ダウンロードサービス付】
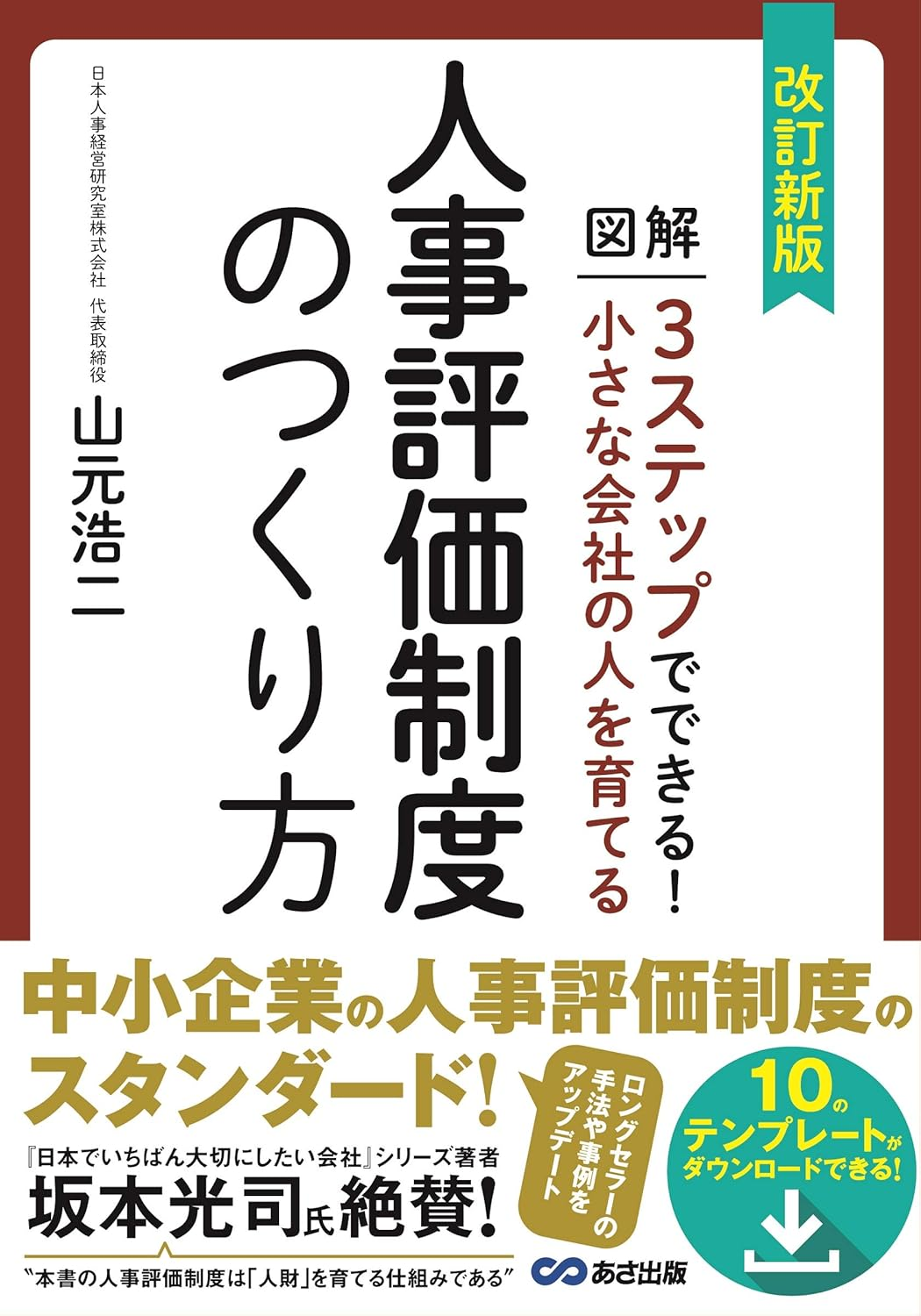
出典:改訂新版 小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方【テンプレート・ダウンロードサービス付】|本|山元 浩二 (著)|あさ出版|通販|Amazon
注目ポイント
- 小規模企業向けに効果的な人事評価制度の構築方法を解説
- ビジョン実現型人事評価制度の制度作りと実践方法を3つのステップで解説
- 10のテンプレートがダウンロードでき、実際の導入作業をスムーズに進めることが可能
料金
1,760円(税込み)
本の基本情報
| 出版社 | あさ出版 |
| 発売日 | 2020/2/14 |
| 著者 | 山元 浩二 |
※2025年3月時点
まとめ
人事評価制度は、企業の成長と従業員のモチベーション向上に不可欠な仕組みです。適切な評価制度を導入することで、公平な処遇や人材育成を実現し、組織の生産性向上につなげることができます。
導入にあたっては、現状の課題把握から評価基準の設定、運用ルールの策定、社内浸透まで、適切な手順を踏むことが大切です。評価制度は一度作って終わりではなく、継続的な見直しと改善が必要です。従業員が納得し、成長できる評価制度を構築し、企業全体の発展を促しましょう。
マーケティング計画を立案する際に利用できるお役立ち資料をお求めの方はこちらからお申し込みください。

koujitsu編集部
マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。





